デイヴィッド・コパーフィールドのコーヒー。 / カフノーツ#17 ― 2005-07-03
カフノーツはコーヒーにまつわる短いお話をあれこれご紹介します。 コーヒーでも飲みながらのんびりお読みください。
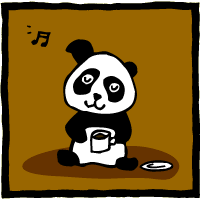
チャールズ・ディケンズの小説『デイヴィッド・コパーフィールド』は、ヴィクトリア朝のイギリスで、両親を亡くした少年コパーフィールドが果敢に成長していく姿を描いた長編小説です。生前に父を亡くし、再婚した母も死んだあと、主人公コパーフィールドは、寄宿舎からロンドンでの重労働へと身を転じます。この時代の下層階級の子どもたちは、過酷な労働環境を強いられる働き手でもありました。10才そこそこでロンドンの倉庫で働くことになったコパーフィールドは、週6シリングの給金で下宿しながら自活をはじめます。働き始めたばかりの彼の関心事は、毎日の食べもののこと。朝ごはんには、パン一個と1ペニー分の牛乳。夜ごはんにはパン一個とわずかなチーズ。
「いま思い出してみても、月曜の朝から土曜日の夜まで、どこの誰からもどんな形にもせよ、忠告一つ、相談一つ、激励一つ、慰め一つ、協力一つ、それに援助の一つも、ぼくはまったくしてもらえなかったんだ」
幼い子どもだった彼は、つい売れ残りのパイを買って食費を使い込んでしまい、空腹をがまんすることで、生活のやりくりを学んでいきます。ごはんがわりにするスグリ入りプディング、気前のいいときには総菜屋の豚肉の乾燥ソーセージか牛肉の赤身料理一皿、パブのチーズとビール一杯。そして懐具合のいいときには、出来合いの半パイントのコーヒーとバター付きパンを一枚。当時のロンドンには、コーヒーハウスの他にコーヒーストールと呼ばれる屋台が街角に多くありました。1840年代には関税引き下げによる値下がりにともなって、コーヒーもお茶も同じくらい日常的な飲み物だったようです。しかし1880年代以降、コーヒーは価格高騰によってイギリスの庶民生活から消えていきます。コパーフィールドの時代は、まだ労働者がコーヒーを飲むことができた幸せな時代。コーヒーストールは、食事をつくる台所もない労働者たちが、食事や飲みものをテイクアウトする場所でした。コパーフィールドが奮発してコーヒーを買ったのも、そんなコーヒーストールのひとつだったはず。コパーフィールドのコーヒーは、憩いや議論に花を咲かせたコーヒーハウスの文化の香りではなく、十九世紀ロンドンの発展を底辺で支えた労働者達のためのコーヒーストールの生活の匂いがしたのではないでしょうか?(カフコンス第19回「モーツァルトとシュタードラーvol.4」プログラム掲載。)
【参考文献】チャールズ・ディケンズ『デイヴィッド・コパーフィールド』(岩波文庫)/谷田博幸『ビクトリア朝百科事典』(河出書房新社)/クリスティン・ヒューズ『十九世紀イギリスの日常生活』(松柏社)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。
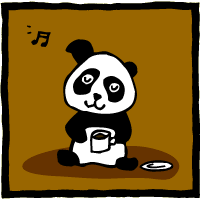
チャールズ・ディケンズの小説『デイヴィッド・コパーフィールド』は、ヴィクトリア朝のイギリスで、両親を亡くした少年コパーフィールドが果敢に成長していく姿を描いた長編小説です。生前に父を亡くし、再婚した母も死んだあと、主人公コパーフィールドは、寄宿舎からロンドンでの重労働へと身を転じます。この時代の下層階級の子どもたちは、過酷な労働環境を強いられる働き手でもありました。10才そこそこでロンドンの倉庫で働くことになったコパーフィールドは、週6シリングの給金で下宿しながら自活をはじめます。働き始めたばかりの彼の関心事は、毎日の食べもののこと。朝ごはんには、パン一個と1ペニー分の牛乳。夜ごはんにはパン一個とわずかなチーズ。
「いま思い出してみても、月曜の朝から土曜日の夜まで、どこの誰からもどんな形にもせよ、忠告一つ、相談一つ、激励一つ、慰め一つ、協力一つ、それに援助の一つも、ぼくはまったくしてもらえなかったんだ」
幼い子どもだった彼は、つい売れ残りのパイを買って食費を使い込んでしまい、空腹をがまんすることで、生活のやりくりを学んでいきます。ごはんがわりにするスグリ入りプディング、気前のいいときには総菜屋の豚肉の乾燥ソーセージか牛肉の赤身料理一皿、パブのチーズとビール一杯。そして懐具合のいいときには、出来合いの半パイントのコーヒーとバター付きパンを一枚。当時のロンドンには、コーヒーハウスの他にコーヒーストールと呼ばれる屋台が街角に多くありました。1840年代には関税引き下げによる値下がりにともなって、コーヒーもお茶も同じくらい日常的な飲み物だったようです。しかし1880年代以降、コーヒーは価格高騰によってイギリスの庶民生活から消えていきます。コパーフィールドの時代は、まだ労働者がコーヒーを飲むことができた幸せな時代。コーヒーストールは、食事をつくる台所もない労働者たちが、食事や飲みものをテイクアウトする場所でした。コパーフィールドが奮発してコーヒーを買ったのも、そんなコーヒーストールのひとつだったはず。コパーフィールドのコーヒーは、憩いや議論に花を咲かせたコーヒーハウスの文化の香りではなく、十九世紀ロンドンの発展を底辺で支えた労働者達のためのコーヒーストールの生活の匂いがしたのではないでしょうか?(カフコンス第19回「モーツァルトとシュタードラーvol.4」プログラム掲載。)
【参考文献】チャールズ・ディケンズ『デイヴィッド・コパーフィールド』(岩波文庫)/谷田博幸『ビクトリア朝百科事典』(河出書房新社)/クリスティン・ヒューズ『十九世紀イギリスの日常生活』(松柏社)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。
コーヒーは幻想曲の味。 / カフノーツ#16 ― 2005-05-22
カフノーツはコーヒーにまつわる短いお話をあれこれご紹介します。 コーヒーでも飲みながらのんびりお読みください。
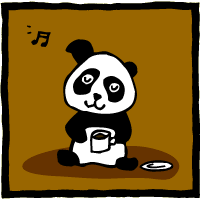
コーヒーを飲むとき、私達はそのコーヒーを飲む空間と時間も一緒に飲んでいます。家で飲む家族とのコーヒー。喫茶店でひとり飲むコーヒー。食事のあとに友人と飲むコーヒー。コーヒーは、その空間と時間に合わせた楽しい儀式を奏でながら、その味を引き立たせるもの。明治時代の物理学者・文学者の寺田寅彦は、随筆「コーヒー哲学序説」の中で、「自分がコーヒーを飲むのは、どうもコーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではない」といいます。彼にとっての「コーヒーの味はコーヒーによって呼び出される幻想曲の味」であり、コーヒーを飲む空間の小道具は、その味を呼び出すための伴奏や前奏のようなもの。テーブルの上の銀器やクリスタルガラスの煌めきが管弦楽の一員となって、美しい調べという味を奏でるのです。だから散らかした居間ではだめ。マーブルかガラスのテーブルに銀器の光る、彼がコーヒーにふさわしいと思う空間でないと、まともなコーヒーの味は味わえない。研究が行き詰まってどうしようもないときに、彼はそうやって「幻想曲の味」のコーヒーを飲みます。すると、「コーヒー茶わんの縁がまさにくちびると相触れようとする瞬間にぱっと頭の中に一道の光が流れ込むような気がすると同時に、やすやすと解決の手掛かりを思いつく」ことがしばしばあるのだとか。一杯のコーヒーは、哲学であり宗教であり芸術。ふだんなにも考えないで飲むコーヒーもそうやって、思考の儀式のように周到に用意された空間で味わってみるのもいいかもしれません。あなたにだけに聴こえる「幻想曲の味」が楽しめるにちがいありません。(カフコンス第17回「ダブルリードでドニゼッティ」プログラム掲載。)
【参考文献】寺田寅彦著「コーヒー哲学序説」/小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集 第四巻』(岩波文庫)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。
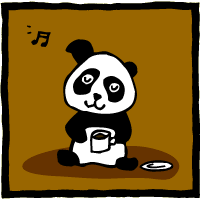
コーヒーを飲むとき、私達はそのコーヒーを飲む空間と時間も一緒に飲んでいます。家で飲む家族とのコーヒー。喫茶店でひとり飲むコーヒー。食事のあとに友人と飲むコーヒー。コーヒーは、その空間と時間に合わせた楽しい儀式を奏でながら、その味を引き立たせるもの。明治時代の物理学者・文学者の寺田寅彦は、随筆「コーヒー哲学序説」の中で、「自分がコーヒーを飲むのは、どうもコーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではない」といいます。彼にとっての「コーヒーの味はコーヒーによって呼び出される幻想曲の味」であり、コーヒーを飲む空間の小道具は、その味を呼び出すための伴奏や前奏のようなもの。テーブルの上の銀器やクリスタルガラスの煌めきが管弦楽の一員となって、美しい調べという味を奏でるのです。だから散らかした居間ではだめ。マーブルかガラスのテーブルに銀器の光る、彼がコーヒーにふさわしいと思う空間でないと、まともなコーヒーの味は味わえない。研究が行き詰まってどうしようもないときに、彼はそうやって「幻想曲の味」のコーヒーを飲みます。すると、「コーヒー茶わんの縁がまさにくちびると相触れようとする瞬間にぱっと頭の中に一道の光が流れ込むような気がすると同時に、やすやすと解決の手掛かりを思いつく」ことがしばしばあるのだとか。一杯のコーヒーは、哲学であり宗教であり芸術。ふだんなにも考えないで飲むコーヒーもそうやって、思考の儀式のように周到に用意された空間で味わってみるのもいいかもしれません。あなたにだけに聴こえる「幻想曲の味」が楽しめるにちがいありません。(カフコンス第17回「ダブルリードでドニゼッティ」プログラム掲載。)
【参考文献】寺田寅彦著「コーヒー哲学序説」/小宮豊隆編『寺田寅彦随筆集 第四巻』(岩波文庫)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。
『シェリ』における甘いココアとクールなコーヒーの関係 / カフノーツ#15 ― 2005-04-24
カフノーツはコーヒーにまつわる短いお話をあれこれご紹介します。 コーヒーでも飲みながらのんびりお読みください。
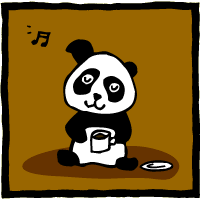
フランスの女性作家コレットの小説『シェリ』は、五十才を越える元高級娼婦レアと親子ほど年のちがうシェリと呼ばれる二十五才の青年との恋の話。
世紀末の裏社交界(ドゥミ・モンド)で活躍した高級娼婦の主人公レアは、自分の金で贅沢をし、館と召使いを取り仕切る、いわば自立した現代的意識を持った冷静で美しい女性。女友達の息子であるシェリとの恋の前半にも、もう若くない自分の身体と心を厳しく律し、冷静な自己判断をしながら、恋と対峙しています。
そしてこの小説の中では、ココアとコーヒーが情景の意味を印象的に物語っているのが興味深いところ。
恋人のシェリと一緒の朝食には、召使いがベッドへ運んでくるブリオッシュとココアがいつものメニュー。甘くて濃いココアの味が二人の時間を包んでいるのがよくわかります。
しかしその若い恋人が出て行くと、レアはてきぱきと身支度をして、召使いに注意を促し、サロンでコーヒーを飲み新聞を読みはじめます。彼女が、恋の情熱を冷静にコントロールしているのがとてもよくわかるシーンです。
恋人シェリが若い娘と結婚して新婚旅行へでかけるときにも、毅然として見守ったレアですが、二人の様子を話す仲間達の集まりで、「このあたしが神経がおかしくなるなんてことあるかしら」と自分でも愕然とするほどに、動揺を受けていたのでした。急いで帰った彼女は、しかし誰にも弱みを見せることなく、召使いに濃くしたココアの中に泡立てた黄身を入れた飲物を注文して、衝撃でがたがたと震える身体を自分で癒します。震える身体をあたたためてくれるのもやはり、甘い恋の時代と同じココア。苦いコーヒーではやはり痛む心を癒せなかったのかもしれません。
物語の最後は、レアがシェリと決別をつけるところで終わります。
その後の続編『シェリの最後』では、戦争から帰還したシェリが主人公。どこにも自分の場所を見いだすことのできないままに、レアの面影を追い求めるシェリの苦悩を描いていますが、こちらではもう甘いココアの香りは消え去り、苦いコーヒーの香りだけがいつも物語のなかを漂っています。
『シェリ』『シェリの最後』の中では、恋の甘さを表現するのがココアならば、コーヒーは苦い現実とでもいうべき存在なのかもしれませんね。(カフコンス第16回「モーツァルトとシュタードラーvol.2」プログラム掲載。)
【参考文献】コレット『シェリ』(岩波文庫)コレット『シェリの最後』(岩波文庫)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。
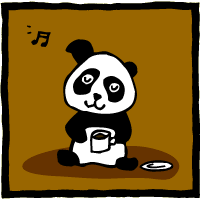
フランスの女性作家コレットの小説『シェリ』は、五十才を越える元高級娼婦レアと親子ほど年のちがうシェリと呼ばれる二十五才の青年との恋の話。
世紀末の裏社交界(ドゥミ・モンド)で活躍した高級娼婦の主人公レアは、自分の金で贅沢をし、館と召使いを取り仕切る、いわば自立した現代的意識を持った冷静で美しい女性。女友達の息子であるシェリとの恋の前半にも、もう若くない自分の身体と心を厳しく律し、冷静な自己判断をしながら、恋と対峙しています。
そしてこの小説の中では、ココアとコーヒーが情景の意味を印象的に物語っているのが興味深いところ。
恋人のシェリと一緒の朝食には、召使いがベッドへ運んでくるブリオッシュとココアがいつものメニュー。甘くて濃いココアの味が二人の時間を包んでいるのがよくわかります。
しかしその若い恋人が出て行くと、レアはてきぱきと身支度をして、召使いに注意を促し、サロンでコーヒーを飲み新聞を読みはじめます。彼女が、恋の情熱を冷静にコントロールしているのがとてもよくわかるシーンです。
恋人シェリが若い娘と結婚して新婚旅行へでかけるときにも、毅然として見守ったレアですが、二人の様子を話す仲間達の集まりで、「このあたしが神経がおかしくなるなんてことあるかしら」と自分でも愕然とするほどに、動揺を受けていたのでした。急いで帰った彼女は、しかし誰にも弱みを見せることなく、召使いに濃くしたココアの中に泡立てた黄身を入れた飲物を注文して、衝撃でがたがたと震える身体を自分で癒します。震える身体をあたたためてくれるのもやはり、甘い恋の時代と同じココア。苦いコーヒーではやはり痛む心を癒せなかったのかもしれません。
物語の最後は、レアがシェリと決別をつけるところで終わります。
その後の続編『シェリの最後』では、戦争から帰還したシェリが主人公。どこにも自分の場所を見いだすことのできないままに、レアの面影を追い求めるシェリの苦悩を描いていますが、こちらではもう甘いココアの香りは消え去り、苦いコーヒーの香りだけがいつも物語のなかを漂っています。
『シェリ』『シェリの最後』の中では、恋の甘さを表現するのがココアならば、コーヒーは苦い現実とでもいうべき存在なのかもしれませんね。(カフコンス第16回「モーツァルトとシュタードラーvol.2」プログラム掲載。)
【参考文献】コレット『シェリ』(岩波文庫)コレット『シェリの最後』(岩波文庫)
西川公子 Hiroko Nishikawa
ウェブやフリペの企画・編集・ライティング。プレイステーションゲーム『L.S.D.』の原案、『東京惑星プラネトキオ』『リズムンフェイス』のシナリオなど。著作に10年分の夢日記をまとめた『Lovely SweetDream』。最近は老人映画研究家。


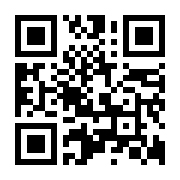
最近のコメント