『ファールプレイ』&『ミカド』 ― 2001-12-07
映画に登場するオペラ作品の数々をとりあげて、
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第14回 思いっきり作り話な『ファール・プレイ』と『ミカド』
~巻き込まれ型サスペンスに巻き込まれたオペレッタ
二回にわたってヴェリズモオペラの名作をご紹介しましたが、そもそも「歌う」という行為からして「現実主義」との共存は難しいわけです。『カヴァレリア・ルスティカーナ』『道化師』の最後の語られるセリフもそれを証明していると言えるし、「衣装を着けろ」にしても結局リアルな人間の「歌」を聴きたいのであって、ちっともリアルじゃない結核で死ぬヒロインの歌だって感動的だし、映画にしてもイタリア映画の庶民のリアリズムはもちろんすごいけど、作りモノの楽しさを満喫できるハチャメチャな映画だって名作だと思うのです。
個人的にオペラや映画を見て人生を考えたりするのは苦手(まあオペラで考えさせられることはほとんどないのですが)だし、メッセージ性の高い映画や音楽もあまり好きではありません。何かを訴えることが映画や音楽の一番の使命だとは思わないし、訴える内容が一番重要であるなら、例えば『シンドラーのリスト』を超える作品はないということになりそう。『シンドラー』だって映画として素晴らしいからこそドキュメント映画を超えられるのではないかと思ったりしています。
さて今回ご紹介するのはそんな事と全く無縁な娯楽作『ファール・プレイ』。20年前に作られた、さらに20年前のヒッチコックとさらにその20年前のマルクス兄弟もネタ元にしたコメディで、見知らぬ男からタバコを預かった女性が法王暗殺計画に巻き込まれていく、いわゆる巻き込まれ型サスペンスなのですが、巻き込まれて可哀想なのは彼女よりもクライマックスの銃撃戦の舞台となるオペラハウス。上演されるのは映画に負けずバカバカしいコミックオペラ『ミカド』です。
それでは『ミカド』ストーリーですが、今回は結末を伏せておきます。このハチャメチャがどう都合よくまとまるのかは見てのお楽しみ。ピンク色の箇所が映画に使われたシーンです。(しかし法王を招くのならもう少しマトモな演目のほうがよいのでは…)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、ティティプ(秩父)の町の侍たちの合唱。そこへ吟遊詩人ナンキプー(実はミカドの皇太子で婚約者カティシャとの結婚から免れるため放浪中)がヤムヤムを訪ねて来る。ヤムヤムと恋に落ちたナンキプーは彼女に後見人のココという婚約者がいたので一度は去ったが、ココが死刑になったと聞いて戻って来たのだ。しかし「ココは死刑を免れたばかりか今では死刑執行長官だ。」と公卿ピシュタシュが説明。そこへヤムヤムが姉妹と登場してナンキプーとの再会を喜ぶが今日はココとの結婚式。ナンキプーはヤムヤムと結ばれないのなら自殺すると嘆くが、「一ヶ月以内に誰かを死刑にしろ」とミカドから命令されているココが「自殺するくらいなら死刑になってくれれば一ヶ月間贅沢をさせてやろう」ともちかけ、ナンキプーも「そのかわりヤムヤムと結婚させてくれ」と交渉成立。そこへ突然カティシャが現れナンキプーに結婚を迫るが、皆は「ナンキプーはヤムヤムと結婚するのだ」とカティシャを無視(「鬼びっくりしゃっくりと」と日本語で合唱)するのでカティシャはミカドに報告に行く。
2幕、ナンキプーとヤムヤムは「一ヶ月後の処刑も一日を一年と思えば三十年の新婚生活」と幸せいっぱいだが「法律では死刑の妻は生き埋め」とわかりまた大騒ぎになる。そこへミカドの行列が到着(「宮さま宮さまお馬の前にひらひらするのは何じゃいな」と日本語で合唱)。ココらティティプの大臣達は「ナンキプーを処刑した」とでっちあげてミカドに報告するが、ナンキプーが実は皇太子とわかり「法律では皇太子殺害犯人には油ゆでの刑」…さてこの結末はいかに?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「誰かが死ぬと巡り巡って自分も死ななくてはならない運命共同体」というのは喜劇の古典的シチュエーションの一つで、サリヴァンと同時代の作曲家シャブリエのオペレッタ『星』も有名です。『星』はそのドタバタ感と洒落た音楽が絶妙なバランスのフランス的傑作、『ミカド』は(一見バカバカしく聞こえるものの実は)精巧な音楽の中にユーモアとパロディの詰め込まれたイギリス的名作と言えるでしょう。『ファール・プレイ』では特にバカバカしい箇所が映画音楽にも使われて何とも楽しく、マンガチックな舞台シーンのエセ日本風演出も笑えます。(映画にも日本人ネタあり。でも「コジャックバンバン」は今の若いヒトには通じないかも。)
それにしてもこの見事なカップリング、こういう映画とオペラのコーディネートはどんな風に行なわれるのでしょう。ちょうどシーズンに上演予定があったのか、道具も壊しちゃうからオペラの最終日終わってから撮影するのか、いやA級映画にそんな心配はいらないのか。(ちなみに映画ではサンフランシスコが舞台ですが演奏のクレジットはニューヨーク・シティ・オペラ。このへんも何かありそう?)『プリティ・ウーマン』や『月の輝く夜に』でさえオペラの舞台はあまり見せずにごまかしていたのに、『ファール・プレイ』はいい意味で無益なお話に贅沢にオペラを持ち込むA級の余裕とセンスがあって、娯楽超大作でありながらB級テイストなところが私のお気に入り。たまには絶対人生考えず泣かずに見られるこんな映画やコミックオペラもいかがですか?
ところでオペラハウスでのドタバタのネタ元と言われているのは『マルクス兄弟オペラは踊る』(1935米)。マルクス兄弟は日本をネタにしたTVのコメディ番組で『ミカド』を使っていたとのことですが、映画での演目は大真面目なヴェルディの『トロヴァトーレ』で、シリアスにやってる所へマルクス兄弟がからんでブチ壊します。またマイク・リー監督の最近の作品『トプシー・ターヴィー』では、なんと『ミカド』作曲中のギルバート&サリヴァンコンビが描かれているそうで、日本でも是非公開してほしいものです。
次回はウディ・アレン・フリークで知られるフル-ト奏者、斎藤和志氏にお話を伺います。お楽しみに。
◇『ファール・プレイ』FOUL PLAY(1978米)
監督:コリン・ヒギンス
音楽:チャールズ・フォックス
出演:ゴールディ・ホーン/チェヴィー・チェイス
◆『ミカド』THE MIKADO(1885初演)全2幕
作曲:サリヴァン A.SULLIVAN(1842-1900)
台本:ギルバート
 川北祥子(stravinsky ensemble)
川北祥子(stravinsky ensemble)
東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
シンバル
『ファールプレイ』にしてもネタ元の『知りすぎていた男』にしても、どうしてシンバルの音と同時に暗殺なのでしょう?シンバル待ってなければ暗殺成功してたかもしれないのにね。殺し屋も音楽わからないといけないから大変。でも実はわかってなくてシンバル奏者の動きを待ってるだけかも…そこで提案。殺し屋を見つけたらシンバル奏者を吹き矢か何かで倒しちゃいましょう。シンバルが鳴らなければ暗殺も実行されません。シンバル奏者は長い休符の間くまなく会場をチェックして、殺し屋を見つけたら鳴らすのをやめること。これで暗殺は激減するはず!
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第14回 思いっきり作り話な『ファール・プレイ』と『ミカド』
~巻き込まれ型サスペンスに巻き込まれたオペレッタ
二回にわたってヴェリズモオペラの名作をご紹介しましたが、そもそも「歌う」という行為からして「現実主義」との共存は難しいわけです。『カヴァレリア・ルスティカーナ』『道化師』の最後の語られるセリフもそれを証明していると言えるし、「衣装を着けろ」にしても結局リアルな人間の「歌」を聴きたいのであって、ちっともリアルじゃない結核で死ぬヒロインの歌だって感動的だし、映画にしてもイタリア映画の庶民のリアリズムはもちろんすごいけど、作りモノの楽しさを満喫できるハチャメチャな映画だって名作だと思うのです。
個人的にオペラや映画を見て人生を考えたりするのは苦手(まあオペラで考えさせられることはほとんどないのですが)だし、メッセージ性の高い映画や音楽もあまり好きではありません。何かを訴えることが映画や音楽の一番の使命だとは思わないし、訴える内容が一番重要であるなら、例えば『シンドラーのリスト』を超える作品はないということになりそう。『シンドラー』だって映画として素晴らしいからこそドキュメント映画を超えられるのではないかと思ったりしています。
さて今回ご紹介するのはそんな事と全く無縁な娯楽作『ファール・プレイ』。20年前に作られた、さらに20年前のヒッチコックとさらにその20年前のマルクス兄弟もネタ元にしたコメディで、見知らぬ男からタバコを預かった女性が法王暗殺計画に巻き込まれていく、いわゆる巻き込まれ型サスペンスなのですが、巻き込まれて可哀想なのは彼女よりもクライマックスの銃撃戦の舞台となるオペラハウス。上演されるのは映画に負けずバカバカしいコミックオペラ『ミカド』です。
それでは『ミカド』ストーリーですが、今回は結末を伏せておきます。このハチャメチャがどう都合よくまとまるのかは見てのお楽しみ。ピンク色の箇所が映画に使われたシーンです。(しかし法王を招くのならもう少しマトモな演目のほうがよいのでは…)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、ティティプ(秩父)の町の侍たちの合唱。そこへ吟遊詩人ナンキプー(実はミカドの皇太子で婚約者カティシャとの結婚から免れるため放浪中)がヤムヤムを訪ねて来る。ヤムヤムと恋に落ちたナンキプーは彼女に後見人のココという婚約者がいたので一度は去ったが、ココが死刑になったと聞いて戻って来たのだ。しかし「ココは死刑を免れたばかりか今では死刑執行長官だ。」と公卿ピシュタシュが説明。そこへヤムヤムが姉妹と登場してナンキプーとの再会を喜ぶが今日はココとの結婚式。ナンキプーはヤムヤムと結ばれないのなら自殺すると嘆くが、「一ヶ月以内に誰かを死刑にしろ」とミカドから命令されているココが「自殺するくらいなら死刑になってくれれば一ヶ月間贅沢をさせてやろう」ともちかけ、ナンキプーも「そのかわりヤムヤムと結婚させてくれ」と交渉成立。そこへ突然カティシャが現れナンキプーに結婚を迫るが、皆は「ナンキプーはヤムヤムと結婚するのだ」とカティシャを無視(「鬼びっくりしゃっくりと」と日本語で合唱)するのでカティシャはミカドに報告に行く。
2幕、ナンキプーとヤムヤムは「一ヶ月後の処刑も一日を一年と思えば三十年の新婚生活」と幸せいっぱいだが「法律では死刑の妻は生き埋め」とわかりまた大騒ぎになる。そこへミカドの行列が到着(「宮さま宮さまお馬の前にひらひらするのは何じゃいな」と日本語で合唱)。ココらティティプの大臣達は「ナンキプーを処刑した」とでっちあげてミカドに報告するが、ナンキプーが実は皇太子とわかり「法律では皇太子殺害犯人には油ゆでの刑」…さてこの結末はいかに?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「誰かが死ぬと巡り巡って自分も死ななくてはならない運命共同体」というのは喜劇の古典的シチュエーションの一つで、サリヴァンと同時代の作曲家シャブリエのオペレッタ『星』も有名です。『星』はそのドタバタ感と洒落た音楽が絶妙なバランスのフランス的傑作、『ミカド』は(一見バカバカしく聞こえるものの実は)精巧な音楽の中にユーモアとパロディの詰め込まれたイギリス的名作と言えるでしょう。『ファール・プレイ』では特にバカバカしい箇所が映画音楽にも使われて何とも楽しく、マンガチックな舞台シーンのエセ日本風演出も笑えます。(映画にも日本人ネタあり。でも「コジャックバンバン」は今の若いヒトには通じないかも。)
それにしてもこの見事なカップリング、こういう映画とオペラのコーディネートはどんな風に行なわれるのでしょう。ちょうどシーズンに上演予定があったのか、道具も壊しちゃうからオペラの最終日終わってから撮影するのか、いやA級映画にそんな心配はいらないのか。(ちなみに映画ではサンフランシスコが舞台ですが演奏のクレジットはニューヨーク・シティ・オペラ。このへんも何かありそう?)『プリティ・ウーマン』や『月の輝く夜に』でさえオペラの舞台はあまり見せずにごまかしていたのに、『ファール・プレイ』はいい意味で無益なお話に贅沢にオペラを持ち込むA級の余裕とセンスがあって、娯楽超大作でありながらB級テイストなところが私のお気に入り。たまには絶対人生考えず泣かずに見られるこんな映画やコミックオペラもいかがですか?
ところでオペラハウスでのドタバタのネタ元と言われているのは『マルクス兄弟オペラは踊る』(1935米)。マルクス兄弟は日本をネタにしたTVのコメディ番組で『ミカド』を使っていたとのことですが、映画での演目は大真面目なヴェルディの『トロヴァトーレ』で、シリアスにやってる所へマルクス兄弟がからんでブチ壊します。またマイク・リー監督の最近の作品『トプシー・ターヴィー』では、なんと『ミカド』作曲中のギルバート&サリヴァンコンビが描かれているそうで、日本でも是非公開してほしいものです。
次回はウディ・アレン・フリークで知られるフル-ト奏者、斎藤和志氏にお話を伺います。お楽しみに。
◇『ファール・プレイ』FOUL PLAY(1978米)
監督:コリン・ヒギンス
音楽:チャールズ・フォックス
出演:ゴールディ・ホーン/チェヴィー・チェイス
◆『ミカド』THE MIKADO(1885初演)全2幕
作曲:サリヴァン A.SULLIVAN(1842-1900)
台本:ギルバート

東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
シンバル
『ファールプレイ』にしてもネタ元の『知りすぎていた男』にしても、どうしてシンバルの音と同時に暗殺なのでしょう?シンバル待ってなければ暗殺成功してたかもしれないのにね。殺し屋も音楽わからないといけないから大変。でも実はわかってなくてシンバル奏者の動きを待ってるだけかも…そこで提案。殺し屋を見つけたらシンバル奏者を吹き矢か何かで倒しちゃいましょう。シンバルが鳴らなければ暗殺も実行されません。シンバル奏者は長い休符の間くまなく会場をチェックして、殺し屋を見つけたら鳴らすのをやめること。これで暗殺は激減するはず!
ウディ・アレン ― 2001-12-28
映画に登場するオペラ作品の数々をとりあげて、
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第15回 ウディ・アレンのせっかく見に行ったくせに最後まで全然見ていなかったり最初で出てきてしまったりするOPERAのすべてについて教えましょう
~それが最高の贅沢なのかそれより現実のドラマが重要なのかはたまた予算の関係か
今回のゲストはウディ・アレン・フリークで知られるフルート奏者、2001年には神戸国際フルートコンクール4位(日本人最高位)、日本音楽コンクール1位と受賞が続き、ますますの活躍が期待される斎藤和志さんです。 正真正銘フルート奏者の斎藤和志さんです…
正真正銘フルート奏者の斎藤和志さんです…
■あの、この写真は…?
これは、人類史上最強のチームであるスペインのレアル・マドリードのレプリカ・ユニフォームで、2000年に欧州チャンピオンズリーグを制したときのものです。偉大なパワーがみなぎってくる気がします。
■…?
実はサッカーが音楽と同じくらいに好きで、音楽家を中心にしたチームにも所属して、かなりのペースで試合をしているのです。実力的には超弱体チームです。なかにはうまい人もいるのですが、ワタシが足をひっぱっています。左サイド(私の受け持ちゾーン)はフリーパスで通行できます。
■手に持っているのは…フルートですか?
斎藤オリジナルのピンク・フルートです。ある酔った晩に勢いでスプレーで塗ってみましたが、意外と好評だったので、ステージでもちょくちょく使っています。
■…「フルート奏者とサッカー」からして「映画監督とクラリネット」以上に意外な組み合わせだと思うのですが。
音楽と映画、スポーツという3つが、20世紀を代表する娯楽だと思うのです。私は、この音楽以外の2つのジャンルについても研究することが、音楽が21世紀の娯楽としてこれまで同様、隆盛を極めることにつながるのではと日夜研究に励んでいるのです。具体的には、映画館や試合場に足を運ぶだけなのですが…たまに仕事をサボッタリして。
■(笑)映画では相当なウディ・アレン・フリークだそうですね。
あの人によって非常に救われた思いがあるのです。学生のころ、本業の音楽がうまくいかず、どうすればいいか深刻な悩みを抱え、自分の性格、キャラクターが音楽家、芸術家向きでないのかと思っていたことがあるのです。どうもまわりの人間で、音楽が得意な奴を見回すと、自然体っていいますか、こうノビノビ生き生きしてて、かつ率直で素直な人間が多くて、やっぱこうでないとだめかな~、と。あるいは、自分はまだ子供過ぎるのか?と。ところが、ウディ・アレンはいい年して「都会が好き。田舎に行くと5分で帰りたくなる」みたいなことを平気で言うワケです。考え方も悲観的でヒネクレて、弱音やグチをブツブツ言うクセに実は自分について相当な自信も持っているし、それで、そのキャラクターのまま、現代の人間をこれほど楽しませることができる。「なんだ、これでいいのか。このまま大人になってしまってもいいのか。」と素直に思えたのでした。これが私にとっては、重大な転機でした。
■そんなお話をうかがうと、あのアレンが何だかカッコよく見えてきます(といってもやっぱりマイケル・ケインやアラン・アルダのほうがカッコいいと思うけど)。特に影響を受けたのはどの作品ですか?
一番印象が強いのは、『ハンナとその姉妹』(1986)と『重罪と軽罪』(1989)でしょうか。ワタシも無神論者なのですが、これによって無神論者がバッハのカンタータや受難曲を演奏して信者の涙を絞ることに関する罪悪感がなくなりました(笑)
■『重罪』によれば罪悪感がなくなればその重罪は裁かれないそうで(笑)しかしその2本は正統派ですね。アレン「フリーク」が選ぶにしてはちょっと予想外なのですが。
え~、なぜ影響があったかといいますと、音楽や演奏には、人柄が表れるなんてよくいいますが、これはまさにそのとおりで。待てよ、するってえと、最高に美しい音楽、モーツァルトなんかを演奏するには、そういう美しい人間でなければならないのか、などと思ってたことがあるのです。実際、そういう人達の演奏が素敵だというのは実感してましたし。他人に思いやりを持てて、人の悲しみを自分のことのように感じてくれるような素直な人間。ああ、素敵な人だな、と思いつつ、そういう人達が安っぽいお涙頂戴映画なんか見てボロボロ泣いてたりするわけで…呆れるやら感心するやらで、どうやら、自分はこうはなれないな、と。自分を見てみると、全く正反対でして。どっちかっつうと他人の失敗なんかそれが深刻であるほどゲラゲラ笑っちまうような人間で。我ながらコレは駄目だと思いましたよ。さて、ほんじゃひとつ宗教でもやってみるか…でも面倒だし人に説教されるのはゴメンだし…などと思っているところに『ハンナ』を見て、あの映画には無神論者であるアレンがかなりきわどく宗教をコケにしているくだりがあるのですが、当時の自分にはピッタリの感覚だったのです。
■まるでマルクス兄弟の映画に救われるアレンのようですね。『重罪』のほうはあまり「救われる映画」ではないように思いますが?
『ハンナ』は、苦労しつつも最終的にみんながハッピーエンドで終わる、まとまりの良い映画なんですけど、『重罪』ではそれが見事にくつがえされてるわけです。善人で必死に頑張ってる愛すべき人間が報われず、悪事を働いてしまい、動揺した人間が最後にそれを乗り越えて(?)幸せを手にする映画。アレン本人の言葉を借りれば、「ハンナ~は少し美しすぎた。現実はもっと複雑で不愉快なものだよ」ということであの映画を撮ったらしいのですが、自分としてもそれは素直に共感できる意見でした。しかし、いい大人が、そんなことわざわざ言うかね…と苦笑しつつ、そう割り切った考えの持ち主が、『ハンナ』や『ラジオ・デイズ』のような愛すべき映画も撮れる、というところが面白かったのです。ん、これはひょっとすると自分もいけるんじゃないかと。
■アレンの映画が多彩なように、音楽もNY&ジャズというイメージですがクラシックも多く使われていますね。特にアレン映画の中で一番深みがあると言っていい『重罪』とシューベルトの後期の弦楽四重奏との組み合わせは見事で、セリフに何度かシューベルトの名を出しておいて中盤の重要なシーンに初めてBGMとして流すのにもヤラレタと思いました。
アレンの音楽のセンスの良さは折り紙つきですが、さりげなく映画の中で言わせる音楽のセリフも渋いところをつくのが気にいってます。『ボギー!オレも男だ』(1972)では、女の子を部屋に呼ぶのに「オスカー・ピーターソンとバルトークのどちらがいいか」みたいなことを言ったり、『世界中がアイ・ラブ・ユー』(1996)では女の子がマーラーの4番が好き、というのを調べて、さりげなく「僕はマーラーの4番が好きで…」みたいに切り出すくだりも最高です。なんで4番なんだ?普通、1番とか5番とか6番だろう?
■(笑)アレンは『私の中のもう一人の私』(1989)にも4番を使っていてお気に入りのようですね。ではかなりのマニアなのかと思えば『セレブリティ』(1998)では「運命」まで使ってしまったり、『私の中の』の一見安易な「ジムノペディ」が実はドビュッシー編というマニアックなものだったり、とにかくセンスとバランスが絶妙ですね。ニューヨーカーにとってのクラシックは「音楽、映画、スポーツ」や美術やお芝居や本やレストランまで話題の娯楽をひと通りチェックする一環なのではと思うのですが、アレンもきっとそんなスタンスなのに、鋭すぎる感性であんな選曲ができてしまうのではないでしょうか。アレン作品にチラッと出てくるクラシックには「全てが揃うNY」を感じますし、逆に舞台がNYでない作品では、『影と霧』(1992)(ヴァイルの「三文オペラ」)や『愛と死』(1975)(プロコフィエフの「キージェ中尉」)などでは意図的に全編クラシックが使われているのではと思います。それぞれ当初グリーグとストラヴィンスキーを使いたかったという説もありますが。
『影と霧』については、ドイツ表現主義風の映画ということで、戦前ドイツの作曲家であるクルト・ヴァイルに絞ってBGMを選曲したんだそうで、ストレートにアレンの感性がこれを選んだ、というよりは理屈が先行している気がします。『愛と死』にストラヴィンスキーを使えなかった、てのはわかる気がします。プロコフィエフとストラヴィンスキー、一見近い存在に見えますが、プロコフィエフが持つ独特の毒や皮肉が、あの映画を他のアレンの初期のコメディと一線を画すカラーにしているのではないでしょうか?ストラヴィンスキーは、その点ちょっとストレートすぎる。前期のバレエはもちろん、後期の新古典主義の作品群でも、プロコフィエフと比べてしまいますと、健全ですね。シーツの安っぽさきわまる亡霊のシーンも、あの曲で妙な味を出してしまう。このへんのセンスは昔からですね。
■『愛と死』の最後の踊り(?)はもうあの曲以外考えられませんけど、ストラヴィンスキーでも初期~中期の民俗色の強いものや「組曲」のような小品ならエセ芸術文学的で合うと思いませんか?でもアレンの好きだったのは「バーゼル」あたりだったらしく、そのへんだとミスマッチでしょうね。最終的にどちらも皮肉なお芝居(背景までそっくりな)のための音楽が採用されているのが計算してるのだかしてないのだか。ところでアレン映画に使われたオペラについてはいかがですか?(『三文オペラ』はオペラというより歌付きのお芝居なので別として。)
オペラについてですと、『ハンナ』が思い浮かびますけれど、『ハンナ』にしましても、ストーリー上、オペラファンの男と恋仲になる関係で使われているだけで、むしろ、3姉妹のそれぞれの主題といいますか、下の妹リーのシーンではバロックが流れ、エイプリルはオペラ(プッチーニ)、ハンナではジャズがかかることによって、3姉妹のキャラクターを書き分けているところが計算が見えて面白いですね。エイプリルは最初のほうのアレンとのデートのシーンでアレンに「君にコール・ポーターなどもったいない」みたいな悪態をつかれるのですが、しかしポーターはもったいなくてプッチーニはいいのかと思うと少し愉快な気持ちです。これがヴェルディやR.シュトラウスではちょっと雰囲気が違うでしょうし、このへんのセンスはやはり流石というべきでしょう。ただ、こうして思うのは、アレンの音楽趣味の中では、オペラは実はそれほど重要なパートは占めてないのでは、と思うのですけれども。クラシックとジャズにはアレンは相当通じていると思うのですが、クラシックで言うなら、むしろ歌モノでない奴のほうに興味があるのではないでしょうか?自身もクラリネットを演奏することもあり、他の映画でのクラシック音楽の引用を見る限り、漠然とそういう思いを抱きましたがいかがでしょうか?
■おっしゃる通りなのですが、いちおう「映画とオペラ」のコラムなもので(汗)…エイプリルはデートで『マノン・レスコー』を見に行くんですが、そもそもパーティでオペラが好きだって意気投合したくせに二人で見つめ合ってワインなんか飲んでる。あと3分でヒロインは死んでオペラも終わるという見せ場なのに全然舞台なんか眼中になくて。このシーンの歌詞「もうすべておしまい!でも死にたくない!」というのはちょうどアレンの心境に重なるものがあって、それが無視されているようでちょっと楽しかったりしました。というのはただのこじつけで(笑)なぜオペラが使われているのか実はよくわかりません。
『マノン・レスコー』について触れますと、このオペラの主人公であるマノンは純粋なんだか悪女なんだかよくわからないなかなかの曲者女性です。若者と情熱的な恋におちたかと思えば、生活苦からいつの間にか金持ちの愛人みたいにおさまっていたり。そこから逃げ出す決心をしたと思ったら、でがけに宝石をいっぱい持って行こうとしてモタついて捕まってしまったり。しかし、妙に可愛らしい感じがしてしまう。そのへんのキャラクターが、『ハンナ』のエイプリルという女性のキャラクターにもフィットした、とアレンは感じたのかも知れないですね。
■マノンの宝石モタつき逃げ遅れは「さっき"贅沢でも愛のない生活は侘びしい"っていうアリアを歌ったばかりじゃないか」とつっこみたくなりますね。そんなマノンに振り回される(?)恋人デ・グリューはいちいち心境を熱唱するアリアの大サービス。テノールを楽しめるオペラだと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、修道院へ向かう途中のマノンは青年騎士デ・グリューに口説かれ、二人は大臣の馬車を盗んで逃げ去る。2幕、マノンはデ・グリューから引き離され大臣の愛人として贅沢に暮らしている。そこへデ・グリューが現れ二人は再び逃げようとするが、マノンが宝石類を持ち出そうとしているうちに大臣と憲兵が現れ、マノンは姦通罪で連行される。3幕、マノンはアメリカに流刑されることになり、デ・グリューはマノンを何とか奪回しようとするが、無理だとわかると船長に哀願して同じ船に乗り込む。4幕、アメリカで二人は荒野に逃れるがマノンは疲労で倒れ、デ・グリューは水を探しに行く。独り残されたマノンは「死にたくない!」と歌い、何も見つからず戻ってきたデ・グリューの腕の中で息絶える。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■『マンハッタン殺人ミステリー』(1993)でアレンとダイアン・キートンが見に行く『さまよえるオランダ人』のゼンタも、思い込みの激しいキートンにフィットしますね。いやこれもただのこじつけです(笑)こちらは見に行ったけれど途中で耐えられなくて出てきてしまうシーンでした。ワーグナーの中では一番短い(2時間強)作品なのに。
彼はユダヤ人ですからね。ワグナーに悪意を持って接してるのでしょうね。どうも日本にいるとピンとこない話なのですけれども。
■だからといって始まって20分で出てくるのも極端ですよ。まだ主役のオランダ人も出てきてないんですよ(そのテンポの遅さがイヤなのか)。それにこの『オランダ人』はさまよえるユダヤ人の話でもあるし(それがイヤなのか)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、嵐の中、入り江にダーラントの船とオランダ人の船が流されて来る。オランダ人は永遠の貞節を誓う女性が現われるまで永遠に海をさまよう呪いをかけられている(オランダ人のモノローグ)。ダーラントはオランダ人の持つ財宝に目がくらみ、ぜひ娘の婿にと自宅へ招く。2幕、ダーラントの娘ゼンタは「伝説のオランダ人」の肖像画を眺め、自分こそ彼のために命を捧げる女性なのだと夢見ている。そこへダーラントがオランダ人を連れて帰って来る。ゼンタは夢の人物が目の前に現れ驚く。オランダ人の求婚にゼンタは永遠の愛を誓う。3幕、ゼンタの恋人エーリックはゼンタに昔の愛の日々を思い出させようとする。それを聞いてしまったオランダ人は絶望して出航するが、ゼンタは「あなたに命を捧げます」と崖から海に身を投げ、二人は救済され天に昇る。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■結局せっかく見に行ったオペラなのに(二組のカップルにはオペラどころではない現実のドラマが進行中とは言え)最後まで全然見ていなかったり最初で出てきてしまったり。やはりアレンはオペラにあまり興味がないのかもしれませんが、斎藤さんはいかがですか?
オペラは大好きですね。映画と同じように、ストーリーがあってセリフ(歌詞)があり、実はシンフォニーや管弦楽曲にくらべて、聴きやすいと思うのですが、日本では、あんまり流行りませんね。ミュージカル映画だと思ってみればいいと思うのですけども。おすすめは…プッチーニが好きなんですよ。適度に安っぽくて馬鹿馬鹿しい部分も含めて。『ラ・ボエーム』が特に好きですね。ストーリーは馬鹿馬鹿しいのですけれども。
■(もしかして「安っぽいお涙頂戴映画」もほんとうはお好きなんじゃないですか?)プッチーニと言えば、アレンも参加した『ニューヨーク・ストーリー』(1989)の中のスコセッシのエピソードにも使われていますが?
『ニューヨーク・ストーリー』は、実は最初の2編は全然興味なくてですね、一話目なんか笛の話のはずなんですが、もうまったくダメで。2編目なんか話の内容も覚えてられませんでした。スコセッシはテンポが遅くて、せっかちな僕にはなかなかつらいものがあります。やはり、アレンくらいのテンポがいいです。
■(※実は1話がスコセッシで2話がコッポラの笛の話。ほんとうにまったく興味がないようで。)わかりました(笑)でもアレン以外の映画で印象的だったオペラやクラシックはありませんか?
それは、やっぱり『アマデウス』(1984)なのです。ワタシのモーツァルト像は、いまでも完全にトム・ハルスです。だからダメなのか???
■いやいや、アマデウス、アレン、斎藤さん、やはり天才には多面性があるということで。ところでその多面性のせいでフルートについてうかがうのをすっかり忘れてました(爆)
フルートは、地元の中学校のブラスで始めたのがきっかけなんですけども、やってみるとこれが面白い楽器なんですよね。オーケストラでも非常に目立つポジションに位置していますし、室内楽やソロでも面白いことがいっぱいできます。それに、クラシックに限らず、ジャズやポップスの世界でもフルートの音色ってのは、合うもんなんですよね。映画音楽の録音の仕事なんかもしたことがありますよ。ワクワクしましたねえ。
■オーケストラでオペラを演奏することもあると思うのですが?
オペラを演奏するときは、オーケストラは普通、オーケストラピットと呼ばれる所で演奏するわけですが、ここが、せまくて暗くてとっても大変なのです。ステージ上で演奏するときと違って、主役はあくまで歌手であり、オーケストラはほとんどの場合、縁の下の力持ちに徹しています。ですが、だからこそ、純粋に「音楽に仕えている」というような、一種独特の快感を味わうことができます。
■最後に、今年は入賞の年でしたが、来年はどんな活動を?
何でも面白いことはやってみたいですが、来年は、オーケストラでの演奏をもう少し活発にしたいと思っています。ですが、できるかぎり、自分で企画できるソロや室内楽もやりたいですね。へそ曲がりで変わった企画を用意したいですね。
■アレンのように毎回期待を魅力的に裏切るような企画を、そしていつか「授賞式を欠席してサッカー」に期待してます。
似たようなことはすでにやっております。絶対的に内緒にしとかないとマズイのですが…
来春アレンの映画デビューと同じ歳を迎える斎藤さん、さあこれから毎年目が離せない!? 次回は斎藤さんもお薦めの『アマデウス』で「OPERAのすべてについて教えましょう」モーツァルト編です。
◇『ハンナとその姉妹』HANNAH AND HER SISTERS(1986米)
監督:ウディ・アレン
出演:ミア・ファロー/ダイアン・ウィースト
◆『マノン・レスコー』MANON LESCAUT(1893初演)4幕
作曲:プッチーニ G.Puccini(1858-1924)
原作:プレヴォーの小説
台本:イッリカ/ジャコーザほか
◇『マンハッタン殺人ミステリー』THE MANHATTAN MURDER MYSTERY(1993米)
監督:ウディ・アレン
出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン
◆『さまよえるオランダ人』DER FLIEGENDE HOLLÄNDER(1843初演)3幕
作曲:ワーグナー R.Wagner(1813-83)
原作:ハイネ/ハウフ等
台本:作曲者自身
 川北祥子(stravinsky ensemble)
川北祥子(stravinsky ensemble)
東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
ワーグナー
とにかく長いワーグナー。今話題のiPodの「1,000songs」「連続再生10時間」にしたって、ワーグナーに換算すると「リングなら3種類!」「連続再生は神々の黄昏の途中まで!」まあ10連奏CDでもダメだった「リング」をバッチリ3種類もポケットに入れておけるのはスゴいことなのか。ちなみに「朝の連続テレビリング」にすれば3ヶ月分です。そんなワーグナーの中で2時間強の『オランダ人』は超コンパクトなのに、アレンは途中で出てきちゃうし「マオマオ編集部員2」さんからは「主役登場まで20分なんてオペラだけだよ」と笑われるし。でも『ゴッドファーザー』の結婚式だって似たようなものじゃない?(と反論しつつ実は90分コメディのほうが好きだけど。)
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第15回 ウディ・アレンのせっかく見に行ったくせに最後まで全然見ていなかったり最初で出てきてしまったりするOPERAのすべてについて教えましょう
~それが最高の贅沢なのかそれより現実のドラマが重要なのかはたまた予算の関係か
今回のゲストはウディ・アレン・フリークで知られるフルート奏者、2001年には神戸国際フルートコンクール4位(日本人最高位)、日本音楽コンクール1位と受賞が続き、ますますの活躍が期待される斎藤和志さんです。

■あの、この写真は…?
これは、人類史上最強のチームであるスペインのレアル・マドリードのレプリカ・ユニフォームで、2000年に欧州チャンピオンズリーグを制したときのものです。偉大なパワーがみなぎってくる気がします。
■…?
実はサッカーが音楽と同じくらいに好きで、音楽家を中心にしたチームにも所属して、かなりのペースで試合をしているのです。実力的には超弱体チームです。なかにはうまい人もいるのですが、ワタシが足をひっぱっています。左サイド(私の受け持ちゾーン)はフリーパスで通行できます。
■手に持っているのは…フルートですか?
斎藤オリジナルのピンク・フルートです。ある酔った晩に勢いでスプレーで塗ってみましたが、意外と好評だったので、ステージでもちょくちょく使っています。
■…「フルート奏者とサッカー」からして「映画監督とクラリネット」以上に意外な組み合わせだと思うのですが。
音楽と映画、スポーツという3つが、20世紀を代表する娯楽だと思うのです。私は、この音楽以外の2つのジャンルについても研究することが、音楽が21世紀の娯楽としてこれまで同様、隆盛を極めることにつながるのではと日夜研究に励んでいるのです。具体的には、映画館や試合場に足を運ぶだけなのですが…たまに仕事をサボッタリして。
■(笑)映画では相当なウディ・アレン・フリークだそうですね。
あの人によって非常に救われた思いがあるのです。学生のころ、本業の音楽がうまくいかず、どうすればいいか深刻な悩みを抱え、自分の性格、キャラクターが音楽家、芸術家向きでないのかと思っていたことがあるのです。どうもまわりの人間で、音楽が得意な奴を見回すと、自然体っていいますか、こうノビノビ生き生きしてて、かつ率直で素直な人間が多くて、やっぱこうでないとだめかな~、と。あるいは、自分はまだ子供過ぎるのか?と。ところが、ウディ・アレンはいい年して「都会が好き。田舎に行くと5分で帰りたくなる」みたいなことを平気で言うワケです。考え方も悲観的でヒネクレて、弱音やグチをブツブツ言うクセに実は自分について相当な自信も持っているし、それで、そのキャラクターのまま、現代の人間をこれほど楽しませることができる。「なんだ、これでいいのか。このまま大人になってしまってもいいのか。」と素直に思えたのでした。これが私にとっては、重大な転機でした。
■そんなお話をうかがうと、あのアレンが何だかカッコよく見えてきます(といってもやっぱりマイケル・ケインやアラン・アルダのほうがカッコいいと思うけど)。特に影響を受けたのはどの作品ですか?
一番印象が強いのは、『ハンナとその姉妹』(1986)と『重罪と軽罪』(1989)でしょうか。ワタシも無神論者なのですが、これによって無神論者がバッハのカンタータや受難曲を演奏して信者の涙を絞ることに関する罪悪感がなくなりました(笑)
■『重罪』によれば罪悪感がなくなればその重罪は裁かれないそうで(笑)しかしその2本は正統派ですね。アレン「フリーク」が選ぶにしてはちょっと予想外なのですが。
え~、なぜ影響があったかといいますと、音楽や演奏には、人柄が表れるなんてよくいいますが、これはまさにそのとおりで。待てよ、するってえと、最高に美しい音楽、モーツァルトなんかを演奏するには、そういう美しい人間でなければならないのか、などと思ってたことがあるのです。実際、そういう人達の演奏が素敵だというのは実感してましたし。他人に思いやりを持てて、人の悲しみを自分のことのように感じてくれるような素直な人間。ああ、素敵な人だな、と思いつつ、そういう人達が安っぽいお涙頂戴映画なんか見てボロボロ泣いてたりするわけで…呆れるやら感心するやらで、どうやら、自分はこうはなれないな、と。自分を見てみると、全く正反対でして。どっちかっつうと他人の失敗なんかそれが深刻であるほどゲラゲラ笑っちまうような人間で。我ながらコレは駄目だと思いましたよ。さて、ほんじゃひとつ宗教でもやってみるか…でも面倒だし人に説教されるのはゴメンだし…などと思っているところに『ハンナ』を見て、あの映画には無神論者であるアレンがかなりきわどく宗教をコケにしているくだりがあるのですが、当時の自分にはピッタリの感覚だったのです。
■まるでマルクス兄弟の映画に救われるアレンのようですね。『重罪』のほうはあまり「救われる映画」ではないように思いますが?
『ハンナ』は、苦労しつつも最終的にみんながハッピーエンドで終わる、まとまりの良い映画なんですけど、『重罪』ではそれが見事にくつがえされてるわけです。善人で必死に頑張ってる愛すべき人間が報われず、悪事を働いてしまい、動揺した人間が最後にそれを乗り越えて(?)幸せを手にする映画。アレン本人の言葉を借りれば、「ハンナ~は少し美しすぎた。現実はもっと複雑で不愉快なものだよ」ということであの映画を撮ったらしいのですが、自分としてもそれは素直に共感できる意見でした。しかし、いい大人が、そんなことわざわざ言うかね…と苦笑しつつ、そう割り切った考えの持ち主が、『ハンナ』や『ラジオ・デイズ』のような愛すべき映画も撮れる、というところが面白かったのです。ん、これはひょっとすると自分もいけるんじゃないかと。
■アレンの映画が多彩なように、音楽もNY&ジャズというイメージですがクラシックも多く使われていますね。特にアレン映画の中で一番深みがあると言っていい『重罪』とシューベルトの後期の弦楽四重奏との組み合わせは見事で、セリフに何度かシューベルトの名を出しておいて中盤の重要なシーンに初めてBGMとして流すのにもヤラレタと思いました。
アレンの音楽のセンスの良さは折り紙つきですが、さりげなく映画の中で言わせる音楽のセリフも渋いところをつくのが気にいってます。『ボギー!オレも男だ』(1972)では、女の子を部屋に呼ぶのに「オスカー・ピーターソンとバルトークのどちらがいいか」みたいなことを言ったり、『世界中がアイ・ラブ・ユー』(1996)では女の子がマーラーの4番が好き、というのを調べて、さりげなく「僕はマーラーの4番が好きで…」みたいに切り出すくだりも最高です。なんで4番なんだ?普通、1番とか5番とか6番だろう?
■(笑)アレンは『私の中のもう一人の私』(1989)にも4番を使っていてお気に入りのようですね。ではかなりのマニアなのかと思えば『セレブリティ』(1998)では「運命」まで使ってしまったり、『私の中の』の一見安易な「ジムノペディ」が実はドビュッシー編というマニアックなものだったり、とにかくセンスとバランスが絶妙ですね。ニューヨーカーにとってのクラシックは「音楽、映画、スポーツ」や美術やお芝居や本やレストランまで話題の娯楽をひと通りチェックする一環なのではと思うのですが、アレンもきっとそんなスタンスなのに、鋭すぎる感性であんな選曲ができてしまうのではないでしょうか。アレン作品にチラッと出てくるクラシックには「全てが揃うNY」を感じますし、逆に舞台がNYでない作品では、『影と霧』(1992)(ヴァイルの「三文オペラ」)や『愛と死』(1975)(プロコフィエフの「キージェ中尉」)などでは意図的に全編クラシックが使われているのではと思います。それぞれ当初グリーグとストラヴィンスキーを使いたかったという説もありますが。
『影と霧』については、ドイツ表現主義風の映画ということで、戦前ドイツの作曲家であるクルト・ヴァイルに絞ってBGMを選曲したんだそうで、ストレートにアレンの感性がこれを選んだ、というよりは理屈が先行している気がします。『愛と死』にストラヴィンスキーを使えなかった、てのはわかる気がします。プロコフィエフとストラヴィンスキー、一見近い存在に見えますが、プロコフィエフが持つ独特の毒や皮肉が、あの映画を他のアレンの初期のコメディと一線を画すカラーにしているのではないでしょうか?ストラヴィンスキーは、その点ちょっとストレートすぎる。前期のバレエはもちろん、後期の新古典主義の作品群でも、プロコフィエフと比べてしまいますと、健全ですね。シーツの安っぽさきわまる亡霊のシーンも、あの曲で妙な味を出してしまう。このへんのセンスは昔からですね。
■『愛と死』の最後の踊り(?)はもうあの曲以外考えられませんけど、ストラヴィンスキーでも初期~中期の民俗色の強いものや「組曲」のような小品ならエセ芸術文学的で合うと思いませんか?でもアレンの好きだったのは「バーゼル」あたりだったらしく、そのへんだとミスマッチでしょうね。最終的にどちらも皮肉なお芝居(背景までそっくりな)のための音楽が採用されているのが計算してるのだかしてないのだか。ところでアレン映画に使われたオペラについてはいかがですか?(『三文オペラ』はオペラというより歌付きのお芝居なので別として。)
オペラについてですと、『ハンナ』が思い浮かびますけれど、『ハンナ』にしましても、ストーリー上、オペラファンの男と恋仲になる関係で使われているだけで、むしろ、3姉妹のそれぞれの主題といいますか、下の妹リーのシーンではバロックが流れ、エイプリルはオペラ(プッチーニ)、ハンナではジャズがかかることによって、3姉妹のキャラクターを書き分けているところが計算が見えて面白いですね。エイプリルは最初のほうのアレンとのデートのシーンでアレンに「君にコール・ポーターなどもったいない」みたいな悪態をつかれるのですが、しかしポーターはもったいなくてプッチーニはいいのかと思うと少し愉快な気持ちです。これがヴェルディやR.シュトラウスではちょっと雰囲気が違うでしょうし、このへんのセンスはやはり流石というべきでしょう。ただ、こうして思うのは、アレンの音楽趣味の中では、オペラは実はそれほど重要なパートは占めてないのでは、と思うのですけれども。クラシックとジャズにはアレンは相当通じていると思うのですが、クラシックで言うなら、むしろ歌モノでない奴のほうに興味があるのではないでしょうか?自身もクラリネットを演奏することもあり、他の映画でのクラシック音楽の引用を見る限り、漠然とそういう思いを抱きましたがいかがでしょうか?
■おっしゃる通りなのですが、いちおう「映画とオペラ」のコラムなもので(汗)…エイプリルはデートで『マノン・レスコー』を見に行くんですが、そもそもパーティでオペラが好きだって意気投合したくせに二人で見つめ合ってワインなんか飲んでる。あと3分でヒロインは死んでオペラも終わるという見せ場なのに全然舞台なんか眼中になくて。このシーンの歌詞「もうすべておしまい!でも死にたくない!」というのはちょうどアレンの心境に重なるものがあって、それが無視されているようでちょっと楽しかったりしました。というのはただのこじつけで(笑)なぜオペラが使われているのか実はよくわかりません。
『マノン・レスコー』について触れますと、このオペラの主人公であるマノンは純粋なんだか悪女なんだかよくわからないなかなかの曲者女性です。若者と情熱的な恋におちたかと思えば、生活苦からいつの間にか金持ちの愛人みたいにおさまっていたり。そこから逃げ出す決心をしたと思ったら、でがけに宝石をいっぱい持って行こうとしてモタついて捕まってしまったり。しかし、妙に可愛らしい感じがしてしまう。そのへんのキャラクターが、『ハンナ』のエイプリルという女性のキャラクターにもフィットした、とアレンは感じたのかも知れないですね。
■マノンの宝石モタつき逃げ遅れは「さっき"贅沢でも愛のない生活は侘びしい"っていうアリアを歌ったばかりじゃないか」とつっこみたくなりますね。そんなマノンに振り回される(?)恋人デ・グリューはいちいち心境を熱唱するアリアの大サービス。テノールを楽しめるオペラだと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、修道院へ向かう途中のマノンは青年騎士デ・グリューに口説かれ、二人は大臣の馬車を盗んで逃げ去る。2幕、マノンはデ・グリューから引き離され大臣の愛人として贅沢に暮らしている。そこへデ・グリューが現れ二人は再び逃げようとするが、マノンが宝石類を持ち出そうとしているうちに大臣と憲兵が現れ、マノンは姦通罪で連行される。3幕、マノンはアメリカに流刑されることになり、デ・グリューはマノンを何とか奪回しようとするが、無理だとわかると船長に哀願して同じ船に乗り込む。4幕、アメリカで二人は荒野に逃れるがマノンは疲労で倒れ、デ・グリューは水を探しに行く。独り残されたマノンは「死にたくない!」と歌い、何も見つからず戻ってきたデ・グリューの腕の中で息絶える。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■『マンハッタン殺人ミステリー』(1993)でアレンとダイアン・キートンが見に行く『さまよえるオランダ人』のゼンタも、思い込みの激しいキートンにフィットしますね。いやこれもただのこじつけです(笑)こちらは見に行ったけれど途中で耐えられなくて出てきてしまうシーンでした。ワーグナーの中では一番短い(2時間強)作品なのに。
彼はユダヤ人ですからね。ワグナーに悪意を持って接してるのでしょうね。どうも日本にいるとピンとこない話なのですけれども。
■だからといって始まって20分で出てくるのも極端ですよ。まだ主役のオランダ人も出てきてないんですよ(そのテンポの遅さがイヤなのか)。それにこの『オランダ人』はさまよえるユダヤ人の話でもあるし(それがイヤなのか)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、嵐の中、入り江にダーラントの船とオランダ人の船が流されて来る。オランダ人は永遠の貞節を誓う女性が現われるまで永遠に海をさまよう呪いをかけられている(オランダ人のモノローグ)。ダーラントはオランダ人の持つ財宝に目がくらみ、ぜひ娘の婿にと自宅へ招く。2幕、ダーラントの娘ゼンタは「伝説のオランダ人」の肖像画を眺め、自分こそ彼のために命を捧げる女性なのだと夢見ている。そこへダーラントがオランダ人を連れて帰って来る。ゼンタは夢の人物が目の前に現れ驚く。オランダ人の求婚にゼンタは永遠の愛を誓う。3幕、ゼンタの恋人エーリックはゼンタに昔の愛の日々を思い出させようとする。それを聞いてしまったオランダ人は絶望して出航するが、ゼンタは「あなたに命を捧げます」と崖から海に身を投げ、二人は救済され天に昇る。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■結局せっかく見に行ったオペラなのに(二組のカップルにはオペラどころではない現実のドラマが進行中とは言え)最後まで全然見ていなかったり最初で出てきてしまったり。やはりアレンはオペラにあまり興味がないのかもしれませんが、斎藤さんはいかがですか?
オペラは大好きですね。映画と同じように、ストーリーがあってセリフ(歌詞)があり、実はシンフォニーや管弦楽曲にくらべて、聴きやすいと思うのですが、日本では、あんまり流行りませんね。ミュージカル映画だと思ってみればいいと思うのですけども。おすすめは…プッチーニが好きなんですよ。適度に安っぽくて馬鹿馬鹿しい部分も含めて。『ラ・ボエーム』が特に好きですね。ストーリーは馬鹿馬鹿しいのですけれども。
■(もしかして「安っぽいお涙頂戴映画」もほんとうはお好きなんじゃないですか?)プッチーニと言えば、アレンも参加した『ニューヨーク・ストーリー』(1989)の中のスコセッシのエピソードにも使われていますが?
『ニューヨーク・ストーリー』は、実は最初の2編は全然興味なくてですね、一話目なんか笛の話のはずなんですが、もうまったくダメで。2編目なんか話の内容も覚えてられませんでした。スコセッシはテンポが遅くて、せっかちな僕にはなかなかつらいものがあります。やはり、アレンくらいのテンポがいいです。
■(※実は1話がスコセッシで2話がコッポラの笛の話。ほんとうにまったく興味がないようで。)わかりました(笑)でもアレン以外の映画で印象的だったオペラやクラシックはありませんか?
それは、やっぱり『アマデウス』(1984)なのです。ワタシのモーツァルト像は、いまでも完全にトム・ハルスです。だからダメなのか???
■いやいや、アマデウス、アレン、斎藤さん、やはり天才には多面性があるということで。ところでその多面性のせいでフルートについてうかがうのをすっかり忘れてました(爆)
フルートは、地元の中学校のブラスで始めたのがきっかけなんですけども、やってみるとこれが面白い楽器なんですよね。オーケストラでも非常に目立つポジションに位置していますし、室内楽やソロでも面白いことがいっぱいできます。それに、クラシックに限らず、ジャズやポップスの世界でもフルートの音色ってのは、合うもんなんですよね。映画音楽の録音の仕事なんかもしたことがありますよ。ワクワクしましたねえ。
■オーケストラでオペラを演奏することもあると思うのですが?
オペラを演奏するときは、オーケストラは普通、オーケストラピットと呼ばれる所で演奏するわけですが、ここが、せまくて暗くてとっても大変なのです。ステージ上で演奏するときと違って、主役はあくまで歌手であり、オーケストラはほとんどの場合、縁の下の力持ちに徹しています。ですが、だからこそ、純粋に「音楽に仕えている」というような、一種独特の快感を味わうことができます。
■最後に、今年は入賞の年でしたが、来年はどんな活動を?
何でも面白いことはやってみたいですが、来年は、オーケストラでの演奏をもう少し活発にしたいと思っています。ですが、できるかぎり、自分で企画できるソロや室内楽もやりたいですね。へそ曲がりで変わった企画を用意したいですね。
■アレンのように毎回期待を魅力的に裏切るような企画を、そしていつか「授賞式を欠席してサッカー」に期待してます。
似たようなことはすでにやっております。絶対的に内緒にしとかないとマズイのですが…
来春アレンの映画デビューと同じ歳を迎える斎藤さん、さあこれから毎年目が離せない!? 次回は斎藤さんもお薦めの『アマデウス』で「OPERAのすべてについて教えましょう」モーツァルト編です。
◇『ハンナとその姉妹』HANNAH AND HER SISTERS(1986米)
監督:ウディ・アレン
出演:ミア・ファロー/ダイアン・ウィースト
◆『マノン・レスコー』MANON LESCAUT(1893初演)4幕
作曲:プッチーニ G.Puccini(1858-1924)
原作:プレヴォーの小説
台本:イッリカ/ジャコーザほか
◇『マンハッタン殺人ミステリー』THE MANHATTAN MURDER MYSTERY(1993米)
監督:ウディ・アレン
出演:ウディ・アレン/ダイアン・キートン
◆『さまよえるオランダ人』DER FLIEGENDE HOLLÄNDER(1843初演)3幕
作曲:ワーグナー R.Wagner(1813-83)
原作:ハイネ/ハウフ等
台本:作曲者自身

東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
ワーグナー
とにかく長いワーグナー。今話題のiPodの「1,000songs」「連続再生10時間」にしたって、ワーグナーに換算すると「リングなら3種類!」「連続再生は神々の黄昏の途中まで!」まあ10連奏CDでもダメだった「リング」をバッチリ3種類もポケットに入れておけるのはスゴいことなのか。ちなみに「朝の連続テレビリング」にすれば3ヶ月分です。そんなワーグナーの中で2時間強の『オランダ人』は超コンパクトなのに、アレンは途中で出てきちゃうし「マオマオ編集部員2」さんからは「主役登場まで20分なんてオペラだけだよ」と笑われるし。でも『ゴッドファーザー』の結婚式だって似たようなものじゃない?(と反論しつつ実は90分コメディのほうが好きだけど。)


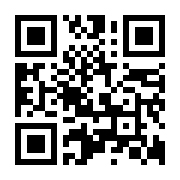
最近のコメント