「星は光りぬ(トスカ)」 ― 2002-04-17
映画に登場するオペラ作品の数々をとりあげて、
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第18回 薄幸のヒーローの未練がましい辞世の歌「星は光りぬ」
~テノール名アリア その2
テノールシリーズ前回は強い男のアリアでしたがこれはかなり例外で、本来テノール役とは、頼りない王子だったり病気のソプラノが死んでいくのを嘆く無力な恋人だったり、と弱々しいもの(?)。映画で言うなら『カサブランカ』のボギーは絶対バリトン、警察署長もバリトンかバスで、活動家=ヒーローとはいえ存在感薄いバーグマンの夫がテノールって感じでしょうか。あっけなく死んじゃう『タイタニック』のディカプリオもきっとテノール、だけど『仮面の男』ならバリトンでしょう。
今回は正統派薄幸のテノールの名アリアです。『トスカ』から「星は光りぬ」、最初に歌詞大意を。
「星はきらめき/大地は香気に満ちていた/庭の戸がきしみ/歩みが砂をかすめ/彼女がかぐわしく入ってきて/私の腕にもたれかかった/ああ!甘いくちづけ!せつない愛撫!/震えながらヴェールをほどくと美しい姿があらわれた!/私の愛の夢は永遠に消えてしまった…/時は過ぎ去り/絶望のうちに私は死ぬ!/今までこれほど生命をいとおしく思ったことはない!」
辞世の歌というわりになかなか未練がましいカヴァラドッシとはどんな人物なのでしょう?『トスカ』ストーリーです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、政治犯アンジェロッティが逃げ込んだ教会では、友人で反体制派の画家カヴァラドッシが聖女の肖像を描いていた。カヴァラドッシは命をかけて彼を助けると誓い、別荘にかくまうことにする。カヴァラドッシの恋人で歌手のトスカは、彼が誰か人と会っていたようなので嫉妬する。教会を訪れた警視総監スカルピアはカヴァラドッシがアンジェロッティをかくまっていると見抜き、トスカの嫉妬をあおってカヴァラドッシの後を追わせ、隠れ家をつきとめようとする。
2幕、連行したカヴァラドッシが口を割らないので、スカルピアはトスカに彼の拷問を見せる。恋人の悲鳴を聞いたトスカはアンジェロッティの居場所を白状してしまう。カヴァラドッシはトスカの裏切りに怒るが、そこへナポレオン大勝が伝えられると勝利を叫び、スカルピアを罵倒するので再び引き立てられる。彼の保釈金はいくらかと訪ねるトスカにスカルピアは貴女をと迫り、トスカは嘆き悩む(アリア「歌に生き恋に生き」)が、アンジェロッティが自殺した事を知らされ要求をのむ決心をする。スカルピアはカヴァラドッシの偽装処刑を命じ、通行許可証を書き、トスカを抱こうと近寄る。その瞬間トスカは「これがトスカの接吻よ」とナイフで刺し、スカルピアは息絶える。
3幕、処刑を前にカヴァラドッシはトスカに辞世の手紙を書く(アリア「星は光りぬ」)。そこへトスカがあらわれて銃殺は空砲だと説明し、二人は愛の勝利を歌う。処刑が行われカヴァラドッシは銃声とともに倒れる。兵士が立ち去り彼を起こそうとトスカが近づくと、彼は本当に殺されていた。そこへスカルピアの死体を発見した追っ手が迫り、トスカは「スカルピアよあの世で!」と叫んで城壁から身を投げる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『トスカ』というからにはトスカが主役なのは仕方ありませんが、テノールはちょっと可哀想すぎ。せっかく拷問に耐えていたのにトスカにすぐばらされ友人は自殺、偽の処刑と聞かされていながら本当に殺され、トスカも「カヴァラドッシ天国で会いましょう!」ではなくスカルピアの名を叫んで死ぬ…でもテノールは登場のたびに高音を聴かせてくれるし、未練がましい歌詞だって歌われるともうこれでもかと泣ける。『トスカ』といえばテノールに期待してしまうのがオペラの不思議です。(よく似た物語『アンドレア・シェニエ』は題名通りテノールが主役。第8回参照。)
さてこの「星は光りぬ」が使われた映画は実話をもとにした2本、新人警官が警察組織の腐敗に立ち向かい正義感ゆえに孤立していく、というシドニー・ルメット監督の社会派ドラマ『セルピコ』と、同性愛の少女の母親殺害事件を描いたピーター・ジャクソン監督作品『乙女の祈り』。
『セルピコ』ではアル・パチーノ演じるセルピコが、まずは『ジャンニスキッキ』のアリアを車の中でかけながらメチャ下手に熱唱し、壮絶な硬派ドラマの中でちょっと息抜きさせてくれます。イタリア系でオペラ好きという設定なのかな、と思わせておいて、中盤には、屋上のテラスで「星は光りぬ」を聴きながら休んでいるセルピコに隣のビルの屋上から女性が話しかけてきて親しくなる、という静かなシーンがあります。私はこの曲とセルピコに共通する「死」のイメージよりも、アリア前半の「庭の戸がきしみ彼女が入ってきた」という美しい回想とオーバーラップしました。
『乙女の祈り』は主人公の二人の少女がテノール歌手マリオ・ランツァのファンという設定。(ランツァは『歌劇王カルーソ』(1951米)で伝説の名歌手カルーソを演じた歌手で、3大テノールの面々もこの映画を見てオペラ歌手を目指したという逸話も。)全編にわたって彼の歌が流れますが、最初はオペレッタ『学生王子』のセレナードなど乙女の憧れのような甘い歌、物語が進むにつれ「死」を思わせるプッチーニとなるあたりが秀逸です。『蝶々夫人』「ハミングコーラス」、『トスカ』「星は光りぬ」、そして少女が「二人きりになりたかったの~あなたは私の愛で命のすべて!」と『ボエーム』4幕のミミを歌うシーンは美しくてどこか怖い。ジャクソン監督は今でこそ『ロード・オブ・ザ・リング』でファンタジーの人ですが当時はホラー&スプラッタのイメージ。題材も異常犯罪なのか多感な少女の純粋さゆえの殺人かというボーダーライン上、作品自体もオペラや空想シーンでかろうじてファンタジー?という微妙なバランス。
ところで今回の2本と前回の『キリングフィールド』もですが、実話と聞くと実際の人物もほんとにオペラが好きだったのか気になりませんか? 脚色だとしたらそれもまた凄い話。セルピコも少女たちも例えばエルビスのファンだってよかったわけなのに、あえてオペラを歌わせたのは?とあれこれ想像するのもまた「映画に出てくるオペラ」ウォッチングの楽しみの一つなのです。
実はもう1本「星は光りぬ」が歌われるというので見てみたい作品があります。『王者のためのアリア』(1979ポーランド)、ポーランドの伝説的プロレスラーの生涯を描いた作品で、彼の勝利の度に客席でオペラ歌手がアリアを高らかに歌うのだそうですが、これも実話なのでしょうか(オペラ歌手のエピソードも??)。
テノールアリア2回シリーズ、これまで2曲がプッチーニになってしまいましたが、「ベスト3」とするなら、「衣装をつけろ」(第13回参照)、「星は光りぬ」、ドニゼッティ『愛の妙薬』から「人知れぬ涙」、あたりが順当なのではないでしょうか。というわけで次回は完結編「人知れぬ涙」です。
◇『セルピコ』SERPICO(1973米)
監督:シドニー・ルメット
音楽:ミキス・テオドラキス
出演:アル・パチーノ/ジョン・ランドルフ
◇『乙女の祈り』HEAVENLY CREATURES(1994ニュージーランド/米)
監督:ピーター・ジャクソン
音楽:ピーター・ダゼント
出演:メラニー・リンスキー/ケイト・ウインスレット
◆『トスカ』TOSCA(1900初演)3幕
作曲:プッチーニG.Puccini(1858-1924)
原作:サルドゥーの同名の戯曲
台本:イッリカ/ジャコーザ
 川北祥子(stravinsky ensemble)
川北祥子(stravinsky ensemble)
東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
フィギュア
オリンピック&世界選手権でフィギュアスケートにしばらくハマっていました。私の大好きなスルツカヤちゃんの『トスカ』は普通なら「歌に生き恋に生き」を選びそうなところを「星は光りぬ」などカヴァラドッシ中心の渋い編集でびっくり、そしてプルシェンコの『カルメン』にはやっぱりベアーズの大進撃を思い出してしまい苦笑(ロシアの人は知らないだろうけど)。ヒューズのエキシビションでの「You'll never walk alone」は映画『乙女の祈り』のエンドタイトルにも使われていた曲で、つくづくアメリカってこういうメッセージ的使い方がうまいなあと感心。残念だったのはこれで見納めのエルドリッジの曲がヴァンゲリスだったこと。クラシックかそれこそ「You'll never walk alone」みたいな曲ならほんとに泣ける美しさだったはずなのに。
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第18回 薄幸のヒーローの未練がましい辞世の歌「星は光りぬ」
~テノール名アリア その2
テノールシリーズ前回は強い男のアリアでしたがこれはかなり例外で、本来テノール役とは、頼りない王子だったり病気のソプラノが死んでいくのを嘆く無力な恋人だったり、と弱々しいもの(?)。映画で言うなら『カサブランカ』のボギーは絶対バリトン、警察署長もバリトンかバスで、活動家=ヒーローとはいえ存在感薄いバーグマンの夫がテノールって感じでしょうか。あっけなく死んじゃう『タイタニック』のディカプリオもきっとテノール、だけど『仮面の男』ならバリトンでしょう。
今回は正統派薄幸のテノールの名アリアです。『トスカ』から「星は光りぬ」、最初に歌詞大意を。
「星はきらめき/大地は香気に満ちていた/庭の戸がきしみ/歩みが砂をかすめ/彼女がかぐわしく入ってきて/私の腕にもたれかかった/ああ!甘いくちづけ!せつない愛撫!/震えながらヴェールをほどくと美しい姿があらわれた!/私の愛の夢は永遠に消えてしまった…/時は過ぎ去り/絶望のうちに私は死ぬ!/今までこれほど生命をいとおしく思ったことはない!」
辞世の歌というわりになかなか未練がましいカヴァラドッシとはどんな人物なのでしょう?『トスカ』ストーリーです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、政治犯アンジェロッティが逃げ込んだ教会では、友人で反体制派の画家カヴァラドッシが聖女の肖像を描いていた。カヴァラドッシは命をかけて彼を助けると誓い、別荘にかくまうことにする。カヴァラドッシの恋人で歌手のトスカは、彼が誰か人と会っていたようなので嫉妬する。教会を訪れた警視総監スカルピアはカヴァラドッシがアンジェロッティをかくまっていると見抜き、トスカの嫉妬をあおってカヴァラドッシの後を追わせ、隠れ家をつきとめようとする。
2幕、連行したカヴァラドッシが口を割らないので、スカルピアはトスカに彼の拷問を見せる。恋人の悲鳴を聞いたトスカはアンジェロッティの居場所を白状してしまう。カヴァラドッシはトスカの裏切りに怒るが、そこへナポレオン大勝が伝えられると勝利を叫び、スカルピアを罵倒するので再び引き立てられる。彼の保釈金はいくらかと訪ねるトスカにスカルピアは貴女をと迫り、トスカは嘆き悩む(アリア「歌に生き恋に生き」)が、アンジェロッティが自殺した事を知らされ要求をのむ決心をする。スカルピアはカヴァラドッシの偽装処刑を命じ、通行許可証を書き、トスカを抱こうと近寄る。その瞬間トスカは「これがトスカの接吻よ」とナイフで刺し、スカルピアは息絶える。
3幕、処刑を前にカヴァラドッシはトスカに辞世の手紙を書く(アリア「星は光りぬ」)。そこへトスカがあらわれて銃殺は空砲だと説明し、二人は愛の勝利を歌う。処刑が行われカヴァラドッシは銃声とともに倒れる。兵士が立ち去り彼を起こそうとトスカが近づくと、彼は本当に殺されていた。そこへスカルピアの死体を発見した追っ手が迫り、トスカは「スカルピアよあの世で!」と叫んで城壁から身を投げる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『トスカ』というからにはトスカが主役なのは仕方ありませんが、テノールはちょっと可哀想すぎ。せっかく拷問に耐えていたのにトスカにすぐばらされ友人は自殺、偽の処刑と聞かされていながら本当に殺され、トスカも「カヴァラドッシ天国で会いましょう!」ではなくスカルピアの名を叫んで死ぬ…でもテノールは登場のたびに高音を聴かせてくれるし、未練がましい歌詞だって歌われるともうこれでもかと泣ける。『トスカ』といえばテノールに期待してしまうのがオペラの不思議です。(よく似た物語『アンドレア・シェニエ』は題名通りテノールが主役。第8回参照。)
さてこの「星は光りぬ」が使われた映画は実話をもとにした2本、新人警官が警察組織の腐敗に立ち向かい正義感ゆえに孤立していく、というシドニー・ルメット監督の社会派ドラマ『セルピコ』と、同性愛の少女の母親殺害事件を描いたピーター・ジャクソン監督作品『乙女の祈り』。
『セルピコ』ではアル・パチーノ演じるセルピコが、まずは『ジャンニスキッキ』のアリアを車の中でかけながらメチャ下手に熱唱し、壮絶な硬派ドラマの中でちょっと息抜きさせてくれます。イタリア系でオペラ好きという設定なのかな、と思わせておいて、中盤には、屋上のテラスで「星は光りぬ」を聴きながら休んでいるセルピコに隣のビルの屋上から女性が話しかけてきて親しくなる、という静かなシーンがあります。私はこの曲とセルピコに共通する「死」のイメージよりも、アリア前半の「庭の戸がきしみ彼女が入ってきた」という美しい回想とオーバーラップしました。
『乙女の祈り』は主人公の二人の少女がテノール歌手マリオ・ランツァのファンという設定。(ランツァは『歌劇王カルーソ』(1951米)で伝説の名歌手カルーソを演じた歌手で、3大テノールの面々もこの映画を見てオペラ歌手を目指したという逸話も。)全編にわたって彼の歌が流れますが、最初はオペレッタ『学生王子』のセレナードなど乙女の憧れのような甘い歌、物語が進むにつれ「死」を思わせるプッチーニとなるあたりが秀逸です。『蝶々夫人』「ハミングコーラス」、『トスカ』「星は光りぬ」、そして少女が「二人きりになりたかったの~あなたは私の愛で命のすべて!」と『ボエーム』4幕のミミを歌うシーンは美しくてどこか怖い。ジャクソン監督は今でこそ『ロード・オブ・ザ・リング』でファンタジーの人ですが当時はホラー&スプラッタのイメージ。題材も異常犯罪なのか多感な少女の純粋さゆえの殺人かというボーダーライン上、作品自体もオペラや空想シーンでかろうじてファンタジー?という微妙なバランス。
ところで今回の2本と前回の『キリングフィールド』もですが、実話と聞くと実際の人物もほんとにオペラが好きだったのか気になりませんか? 脚色だとしたらそれもまた凄い話。セルピコも少女たちも例えばエルビスのファンだってよかったわけなのに、あえてオペラを歌わせたのは?とあれこれ想像するのもまた「映画に出てくるオペラ」ウォッチングの楽しみの一つなのです。
実はもう1本「星は光りぬ」が歌われるというので見てみたい作品があります。『王者のためのアリア』(1979ポーランド)、ポーランドの伝説的プロレスラーの生涯を描いた作品で、彼の勝利の度に客席でオペラ歌手がアリアを高らかに歌うのだそうですが、これも実話なのでしょうか(オペラ歌手のエピソードも??)。
テノールアリア2回シリーズ、これまで2曲がプッチーニになってしまいましたが、「ベスト3」とするなら、「衣装をつけろ」(第13回参照)、「星は光りぬ」、ドニゼッティ『愛の妙薬』から「人知れぬ涙」、あたりが順当なのではないでしょうか。というわけで次回は完結編「人知れぬ涙」です。
◇『セルピコ』SERPICO(1973米)
監督:シドニー・ルメット
音楽:ミキス・テオドラキス
出演:アル・パチーノ/ジョン・ランドルフ
◇『乙女の祈り』HEAVENLY CREATURES(1994ニュージーランド/米)
監督:ピーター・ジャクソン
音楽:ピーター・ダゼント
出演:メラニー・リンスキー/ケイト・ウインスレット
◆『トスカ』TOSCA(1900初演)3幕
作曲:プッチーニG.Puccini(1858-1924)
原作:サルドゥーの同名の戯曲
台本:イッリカ/ジャコーザ

東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
フィギュア
オリンピック&世界選手権でフィギュアスケートにしばらくハマっていました。私の大好きなスルツカヤちゃんの『トスカ』は普通なら「歌に生き恋に生き」を選びそうなところを「星は光りぬ」などカヴァラドッシ中心の渋い編集でびっくり、そしてプルシェンコの『カルメン』にはやっぱりベアーズの大進撃を思い出してしまい苦笑(ロシアの人は知らないだろうけど)。ヒューズのエキシビションでの「You'll never walk alone」は映画『乙女の祈り』のエンドタイトルにも使われていた曲で、つくづくアメリカってこういうメッセージ的使い方がうまいなあと感心。残念だったのはこれで見納めのエルドリッジの曲がヴァンゲリスだったこと。クラシックかそれこそ「You'll never walk alone」みたいな曲ならほんとに泣ける美しさだったはずなのに。
「誰も寝てはならぬ(トゥーランドット)」 ― 2002-03-13
映画に登場するオペラ作品の数々をとりあげて、
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第17回 眠れぬ男たちの「誰も寝てはならぬ」
~テノール名アリア その1
オペラに特別興味がなくても、ワールドカップの開会式で聴いた3大テノールはかっこよかった、なんて思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。でも歌詞がピンと来なかったりした経験はありませんか?オペラのアリアは歌詞が台本の一部分なので、一曲だけ聴いても内容がよく解らないこともあります。それでも充分楽しめますが、オペラの背景を踏まえて聴けばもっと感動できるかも、ということで今回から3回シリーズでテノールの名アリアをご紹介したいと思います。1曲目は3大テノールでも特に注目の集まる『トゥーランドット』の王子のアリア「誰も寝てはならぬ」。では歌詞大意からどうぞ。
「誰も寝てはならぬ!か…/姫よ、あなたも冷たい部屋で愛と希望に震える星をご覧なさい!/しかし秘密は私の胸の中、私の名前は誰も知らない!/いや、あなたの唇に私が告げるのだ、光が輝く時に!/そして私の口づけがあなたを私のものにする時に!/夜よ消えろ!星よ沈め!夜明けに私は勝つのだ!」
短いアリアなので歌詞はこれだけ(長くても延々繰り返しだったりしますが)。何となくどんな場面か想像できたでしょうか?それでは『トゥーランドット』ストーリーの正解を。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、北京。トゥーランドット姫は三つの謎を解いた王子と結婚するが謎が解けない者は打ち首、と定められている。謎解きに失敗した求婚者の処刑を見ようと集まった人々の中で、敵を恐れて名を隠した異国の王子は、同じく身分を隠す父ティムールとその付き添いのリューに再会する。王子は処刑を見てもひるむ事なく、彼を愛するリューが泣いて止めるのも聞かず、姫の美しさに見愡れて謎解きへの挑戦を宣言する。
2幕1場、大臣たちは処刑ではなく結婚の準備をしたいものだと願っている。2場、皇帝と姫が登場し謎かけが始まる。王子がこれまで誰も解けなかった三つの謎を簡単に解いてみせると、姫は結婚の定めは無効にと皇帝に訴えるが皇帝は却下する。王子は夜明けまでに自分の名前を解きあかせば姫に命を捧げよう、と謎かけを返す。
3幕1場、誰も寝てはならぬという姫の命で人々は寝ずに王子の名前を調べている。王子は「私の名前は誰も知らない!夜明けに私は勝つのだ!」と歌う。ティムールとリューは王子と話していたからと引き立てられ拷問を受けるが、リューは自分だけが王子の名前を知っているとティムールをかばい、剣を奪って自殺する。姫は王子に去ってくれと頼むが、王子が口づけすると姫の心は溶け涙を流す。だが彼がダッタンの王子カラフだと名乗ると姫は名前がわかったと叫び、カラフはあなたの勝ちだと認める。3幕2場、しかし姫は人々の見守る中「この異国の王子の名前がわかりました。その名は愛!」と告げ、皆の歓喜の大合唱で幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『トゥーランドット』はプッチーニお得意の異国物語ですが、同じアジアの蝶々夫人とは対照的にトゥーランドットは強くてコワいお姫様。しかしカラフはその上を行くつわもので、自分を慕う女性が殺されても嘆くアリアを歌うこともなく(この点はリューが可哀想すぎると反感も?)、栄誉も愛も手に入れハッピーエンド(悲劇のヒーローとして立派に死んでいく役は多いが)、これほど強いテノール役は他にないと言っていいでしょう。題名はカラフの台詞ではなく「誰も寝てはならぬ」という命令とそれを聞いて必死で彼の名を調べようとする人々を皮肉ったもので、むしろキーワードと聴き所は最後に高らかに歌われる「私は勝つ!」。フィナーレでも同じ旋律が「栄光あれ!」と大合唱され、もう一度感動すること必至です。
さて映画のほうはこの「誰も寝てはならぬ」がそれぞれ違った使われ方をした3本です。まずは『ニューヨーク・ストーリー』(M.スコセッシ、F.コッポラ、W.アレンの短編オムニバスで、コッポラ監督の第2話には女の子のお世話役の男性が「女心の歌」を歌っている場面も)からスコセッシ監督による第1話『ライフレッスン』。画家ニック・ノルティは住み込みのアシスタントを愛しているが、彼女の心はもう彼から離れていて新しい恋人を部屋に呼び、眠れないノルティは「誰も寝てはならぬ」を聴く。愛の勝利の歌を敗北した男が聴く皮肉。ノルティが絵を描く時にはロックをガンガン鳴らすのもこの曲を際立たせていました。スコセッシ監督といえば『レイジングブル』(1980米)のマスカーニや、『ファウスト』の舞台から始まる『エイジ・オブ・イノセンス』(1993米)(『トロヴァトーレ』の舞台から始まるヴィスコンティの『夏の嵐』(1954伊)のパロディ?)などでのオペラも有名。
シェール、スーザン・サランドン、ミシェル・ファイファーという熟女3人組のホラーコメディ(?)『イーストウィックの魔女たち』では、ある日突然現われた妖しい男ジャック・ニコルソンと3人の過ごすステキな一夜(?)に「誰も寝てはならぬ」が流れます。あのジョン・ウィリアムスならどんな曲でも自在に書けてしまいそうなのに敢えて既成曲を使っているだけあって「自信に満ちた男のアリア」が本当にぴったり。曲の陶酔感とフーセンやスローモーションがこの濃いメンツをファンタジックに見せてしまいます。ミュージカル版『イーストウィックの魔女たち』でもこのシーンはフライングが楽しめる見せ場なのだそうで、どんな音楽が流れるのか聴いてみたいです。
『キリング・フィールド』で「誰も寝てはならぬ」を聴くのはサム・ウォーターストン。カンボジア内乱を取材していたタイムズ記者ウォーターストンは政権崩壊で国外へ脱出し、このルポでピューリッツァ賞を受賞するが、長く彼に同行していたカンボジア人助手は現地に取り残される。助手の身を案じて眠れない彼は混乱するカンボジアの様子をテレビで見ながらこの曲を聴く。慌てふためく人々を嘲笑するかのようなカラフのアリアが、名声を得て安全なアメリカでカンボジアの映像を眺める自分の姿に重なってしまう彼の苦々しさをも表わした、ひとひねり効いた使われ方でした。
(個人的に『キリング・フィールド』の最後に流れる「イマジン」はちょっとがっかり。「誰も寝てはならぬ」の見事な選曲と比べるとあまりにも安易では…『ライフ・レッスン』で流れる「青い影」は曲自体は好きになれないけど、この曲のカッコ悪さをさらけ出す感じ?がノルティのキャラクターにも通じるようで納得させられるし、エンドタイトルでは一緒に口ずさんでしまいます。)
ところでノルティは『イーストウィック』の監督ジョージ・ミラーの『ロレンツォのオイル』(1992米)で難病の息子を救うためにオイルを研究する両親をサランドンと演じ、この作品では『ノルマ』などのオペラが全編に流れていました。サランドンは『アトランティックシティ』(1980仏/加)でも『ノルマ』の「女神」という役どころ。またシェールは『月の輝く夜に』(1987米)、ファイファーは『エイジ・オブ・イノセンス』、ニコルソンは『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1981米)、『女と男の名誉』(1985米)、ウォーターストンは『ハンナとその姉妹』(1986米)など、こうして見るとみんな他の映画でもオペラの似合っている人ばかりです。
次回はテノール珠玉の名アリアシリーズその2、オペラが最高に似合うアル・パチーノの『セルピコ』などに使われた『トスカ』の「星は光りぬ」です。
◇『ニューヨーク・ストーリー』NEW YORK STORIES(1989米)
Segement 1 "Life Lessons"
監督:マーティン・スコセッシ
出演:ニック・ノルティ/ロザンナ・アークエット
◇『イーストウィックの魔女たち』THE WITCHES OF EASTWICK(1987米)
監督:ジョージ・ミラー
音楽:ジョン・ウイリアムス
出演:ジャック・ニコルソン/シェール
◇『キリング・フィールド』THE KILLING FIELDS(1984米)
監督:ローランド・ジョフィ
音楽:マイク・オールドフィールド
出演:サム・ウォーターストン/ハイン・S・ニョール
◆『トゥーランドット』TURANDOT(1926初演)3幕5場
作曲:プッチーニG.Puccini(1858-1924)
補作:プッチーニの草稿によりアルファーノF.Alfano(1876-1954)
原作:ゴッツィの同名の戯曲と「千夜一夜物語」
台本:アダーミ/シモーニ
 川北祥子(stravinsky ensemble)
川北祥子(stravinsky ensemble)
東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第17回 眠れぬ男たちの「誰も寝てはならぬ」
~テノール名アリア その1
オペラに特別興味がなくても、ワールドカップの開会式で聴いた3大テノールはかっこよかった、なんて思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。でも歌詞がピンと来なかったりした経験はありませんか?オペラのアリアは歌詞が台本の一部分なので、一曲だけ聴いても内容がよく解らないこともあります。それでも充分楽しめますが、オペラの背景を踏まえて聴けばもっと感動できるかも、ということで今回から3回シリーズでテノールの名アリアをご紹介したいと思います。1曲目は3大テノールでも特に注目の集まる『トゥーランドット』の王子のアリア「誰も寝てはならぬ」。では歌詞大意からどうぞ。
「誰も寝てはならぬ!か…/姫よ、あなたも冷たい部屋で愛と希望に震える星をご覧なさい!/しかし秘密は私の胸の中、私の名前は誰も知らない!/いや、あなたの唇に私が告げるのだ、光が輝く時に!/そして私の口づけがあなたを私のものにする時に!/夜よ消えろ!星よ沈め!夜明けに私は勝つのだ!」
短いアリアなので歌詞はこれだけ(長くても延々繰り返しだったりしますが)。何となくどんな場面か想像できたでしょうか?それでは『トゥーランドット』ストーリーの正解を。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1幕、北京。トゥーランドット姫は三つの謎を解いた王子と結婚するが謎が解けない者は打ち首、と定められている。謎解きに失敗した求婚者の処刑を見ようと集まった人々の中で、敵を恐れて名を隠した異国の王子は、同じく身分を隠す父ティムールとその付き添いのリューに再会する。王子は処刑を見てもひるむ事なく、彼を愛するリューが泣いて止めるのも聞かず、姫の美しさに見愡れて謎解きへの挑戦を宣言する。
2幕1場、大臣たちは処刑ではなく結婚の準備をしたいものだと願っている。2場、皇帝と姫が登場し謎かけが始まる。王子がこれまで誰も解けなかった三つの謎を簡単に解いてみせると、姫は結婚の定めは無効にと皇帝に訴えるが皇帝は却下する。王子は夜明けまでに自分の名前を解きあかせば姫に命を捧げよう、と謎かけを返す。
3幕1場、誰も寝てはならぬという姫の命で人々は寝ずに王子の名前を調べている。王子は「私の名前は誰も知らない!夜明けに私は勝つのだ!」と歌う。ティムールとリューは王子と話していたからと引き立てられ拷問を受けるが、リューは自分だけが王子の名前を知っているとティムールをかばい、剣を奪って自殺する。姫は王子に去ってくれと頼むが、王子が口づけすると姫の心は溶け涙を流す。だが彼がダッタンの王子カラフだと名乗ると姫は名前がわかったと叫び、カラフはあなたの勝ちだと認める。3幕2場、しかし姫は人々の見守る中「この異国の王子の名前がわかりました。その名は愛!」と告げ、皆の歓喜の大合唱で幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『トゥーランドット』はプッチーニお得意の異国物語ですが、同じアジアの蝶々夫人とは対照的にトゥーランドットは強くてコワいお姫様。しかしカラフはその上を行くつわもので、自分を慕う女性が殺されても嘆くアリアを歌うこともなく(この点はリューが可哀想すぎると反感も?)、栄誉も愛も手に入れハッピーエンド(悲劇のヒーローとして立派に死んでいく役は多いが)、これほど強いテノール役は他にないと言っていいでしょう。題名はカラフの台詞ではなく「誰も寝てはならぬ」という命令とそれを聞いて必死で彼の名を調べようとする人々を皮肉ったもので、むしろキーワードと聴き所は最後に高らかに歌われる「私は勝つ!」。フィナーレでも同じ旋律が「栄光あれ!」と大合唱され、もう一度感動すること必至です。
さて映画のほうはこの「誰も寝てはならぬ」がそれぞれ違った使われ方をした3本です。まずは『ニューヨーク・ストーリー』(M.スコセッシ、F.コッポラ、W.アレンの短編オムニバスで、コッポラ監督の第2話には女の子のお世話役の男性が「女心の歌」を歌っている場面も)からスコセッシ監督による第1話『ライフレッスン』。画家ニック・ノルティは住み込みのアシスタントを愛しているが、彼女の心はもう彼から離れていて新しい恋人を部屋に呼び、眠れないノルティは「誰も寝てはならぬ」を聴く。愛の勝利の歌を敗北した男が聴く皮肉。ノルティが絵を描く時にはロックをガンガン鳴らすのもこの曲を際立たせていました。スコセッシ監督といえば『レイジングブル』(1980米)のマスカーニや、『ファウスト』の舞台から始まる『エイジ・オブ・イノセンス』(1993米)(『トロヴァトーレ』の舞台から始まるヴィスコンティの『夏の嵐』(1954伊)のパロディ?)などでのオペラも有名。
シェール、スーザン・サランドン、ミシェル・ファイファーという熟女3人組のホラーコメディ(?)『イーストウィックの魔女たち』では、ある日突然現われた妖しい男ジャック・ニコルソンと3人の過ごすステキな一夜(?)に「誰も寝てはならぬ」が流れます。あのジョン・ウィリアムスならどんな曲でも自在に書けてしまいそうなのに敢えて既成曲を使っているだけあって「自信に満ちた男のアリア」が本当にぴったり。曲の陶酔感とフーセンやスローモーションがこの濃いメンツをファンタジックに見せてしまいます。ミュージカル版『イーストウィックの魔女たち』でもこのシーンはフライングが楽しめる見せ場なのだそうで、どんな音楽が流れるのか聴いてみたいです。
『キリング・フィールド』で「誰も寝てはならぬ」を聴くのはサム・ウォーターストン。カンボジア内乱を取材していたタイムズ記者ウォーターストンは政権崩壊で国外へ脱出し、このルポでピューリッツァ賞を受賞するが、長く彼に同行していたカンボジア人助手は現地に取り残される。助手の身を案じて眠れない彼は混乱するカンボジアの様子をテレビで見ながらこの曲を聴く。慌てふためく人々を嘲笑するかのようなカラフのアリアが、名声を得て安全なアメリカでカンボジアの映像を眺める自分の姿に重なってしまう彼の苦々しさをも表わした、ひとひねり効いた使われ方でした。
(個人的に『キリング・フィールド』の最後に流れる「イマジン」はちょっとがっかり。「誰も寝てはならぬ」の見事な選曲と比べるとあまりにも安易では…『ライフ・レッスン』で流れる「青い影」は曲自体は好きになれないけど、この曲のカッコ悪さをさらけ出す感じ?がノルティのキャラクターにも通じるようで納得させられるし、エンドタイトルでは一緒に口ずさんでしまいます。)
ところでノルティは『イーストウィック』の監督ジョージ・ミラーの『ロレンツォのオイル』(1992米)で難病の息子を救うためにオイルを研究する両親をサランドンと演じ、この作品では『ノルマ』などのオペラが全編に流れていました。サランドンは『アトランティックシティ』(1980仏/加)でも『ノルマ』の「女神」という役どころ。またシェールは『月の輝く夜に』(1987米)、ファイファーは『エイジ・オブ・イノセンス』、ニコルソンは『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1981米)、『女と男の名誉』(1985米)、ウォーターストンは『ハンナとその姉妹』(1986米)など、こうして見るとみんな他の映画でもオペラの似合っている人ばかりです。
次回はテノール珠玉の名アリアシリーズその2、オペラが最高に似合うアル・パチーノの『セルピコ』などに使われた『トスカ』の「星は光りぬ」です。
◇『ニューヨーク・ストーリー』NEW YORK STORIES(1989米)
Segement 1 "Life Lessons"
監督:マーティン・スコセッシ
出演:ニック・ノルティ/ロザンナ・アークエット
◇『イーストウィックの魔女たち』THE WITCHES OF EASTWICK(1987米)
監督:ジョージ・ミラー
音楽:ジョン・ウイリアムス
出演:ジャック・ニコルソン/シェール
◇『キリング・フィールド』THE KILLING FIELDS(1984米)
監督:ローランド・ジョフィ
音楽:マイク・オールドフィールド
出演:サム・ウォーターストン/ハイン・S・ニョール
◆『トゥーランドット』TURANDOT(1926初演)3幕5場
作曲:プッチーニG.Puccini(1858-1924)
補作:プッチーニの草稿によりアルファーノF.Alfano(1876-1954)
原作:ゴッツィの同名の戯曲と「千夜一夜物語」
台本:アダーミ/シモーニ

東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
アマデウス ― 2002-02-08
映画に登場するオペラ作品の数々をとりあげて、
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第16回 アマデウスのいろいろありすぎてどれから見たらいいかわからないOPERAのすべてについて教えましょう
~で結局死因は?
『アマデウス』(1994米)はモーツァルトのミドルネームを広く知らしめ、サリエリにモーツァルト殺しのイメージを定着させました。偶然同年の『くたばれアマデウス!』(1984独)でもモーツァルト殺しの意外な真犯人が論じられました。死因はどちらもフィクションですがオペラに関するエピソードは事実に基づいているので、今回はこの二本に登場するモーツァルトのオペラベスト5『後宮からの誘拐』『フィガロの結婚』『ドン・ジョヴァンニ』『コシ・ファン・トゥッテ』『魔笛』を一挙にご紹介しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『後宮からの誘拐』
貴族の娘コンスタンツェとその召し使いブロンデは航海中に海賊の捕虜となり、トルコの太守セリムに売られ彼の後宮に囲われているが、コンスタンツェは言い寄るセリムを断固として拒否し続けている。そこへコンスタンツェの恋人ベルモンテが召し使いペドリロから居場所を知らされて救出にかけつける。見張りのオスミンも簡単に眠らせ4人の脱出計画は成功するかに見えたがあと一息の所で捕まってしまい、さらにベルモンテの父がセリムと宿敵同士とわかり絶体絶命となるが、セリムは「悪には善によって報いよう」と4人を釈放し、全員がセリムの徳を讃えて幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あのトム・ハルスのモーツァルトに「ハーレムが舞台で面白いんだよ」なんて言われると期待してしまいますがそれほどの話でもありません。「囲われている」と言いつつ、当時のお芝居では女性は「誘惑の危機」から「すんでのところで」逃れるというお約束になっていますからコンスタンツェも「まだ」無事で、ご丁寧にも「どんな拷問も死も(貞操を失うことに比べれば)怖くありません!」と立派なアリアを歌ってくれます。『アマデウス』に登場したのはこの2幕のアリアと3幕フィナーレ。フィナーレの意外な釈放は当時の「寛容な啓蒙君主」に対するゴマスリと言われ、つまりヨゼフ2世も大満足というわけです(音が多いとか文句言ってたのはテレ隠し?)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『フィガロの結婚』(ストーリーは第9回参照)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このコメディが「階級の間の対立を生む」(ヨゼフ2世)という実感は現在ではあまりありませんが、『くたばれ』での「伯爵がダンスならいつでもギターを弾いてやろう」というフィガロのアリアはとても皮肉っぽく聞こえます。『アマデウス』に出てきたのは冒頭の二重唱(リハーサル)、3幕フィナーレの結婚のバレエ、伯爵が許しを乞う4幕フィナーレ。フィナーレではアクビが大問題になっていましたが、3時間以上も聴いていれば面白くても疲れますよね?観に行く時には食事にも要注意。お腹がすいていては長時間耐えられないしお腹一杯だと眠ってしまうし…
『フィガロ』は特に有名なので映画への引用も数えきれませんが、その中で私のちょっと気になるのが4幕のバルバリーナの「なくしてしまったわ」というアリア。オペラの中では手紙を止めていたピンを落としてしまって探しているだけの小さな曲(貞操を失くしたという説もあるものの)ですが、『カオスシチリア物語』(1984伊)では母親の歌っていた曲として、『伴奏者』(1992仏)では歌手の夫のお気に入りの曲として、深い悲しみをもって流れます。ヨーロッパ映画でのこの使われ方には何か特別の意味があるのでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『ドン・ジョヴァンニ』
騎士長の屋敷に押し入ったドン・ジョヴァンニは、娘アンナを誘惑しようとして騎士長と決闘になり殺してしまう。アンナは恋人オッターヴィオとともに復讐を誓う。ドン・ジョヴァンニが次に声をかけたのは偶然にも彼に捨てられて追ってきたエルヴィラだったが、ドン・ジョヴァンニの従僕レポレロがうまく主人を逃がす。ドン・ジョヴァンニは村の花嫁ツェルリーナも誘惑するが失敗、ツェルリーナと花婿マゼットも彼を追う。皆から逃げたドン・ジョヴァンニの所へ騎士長の石像が現われ懺悔するように命令するが、ドン・ジョヴァンニが決然と断ると地獄の火が彼を包み込む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このオペラ最大の見せ場はやはり「ドン・ジョヴァンニの地獄落ち」でしょう。『虚栄のかがり火』(1990米)では逮捕目前まで追い詰められたトムハンクスが『ドン・ジョヴァンニ』を観に行き、地獄のかがり火の恐ろしいシーンに自分の姿を重ねていました。『アマデウス』でも煙が吹き出す演出(当時に可能?)。対照的にとても美しくて人気なのが二重唱「手をとりあって」。ジョニー・デップが自分をドンファンと思い込んでいる青年を演じる『ドンファン』(1995米)ではあくまでもロマンティックに使われていましたが、実際には誘惑するドン・ジョヴァンニと結婚式当日というのに誘いに乗ってしまうツェルリーナの二重唱なのでもう少し複雑な意味合い。『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1981米)のジェシカ・ラングは夫が寝室でこの曲のレコードをかけているのでニコルソンの誘いに乗れません。『バベットの晩餐会』(1987デンマーク)では歌のレッスンでこの曲をデュエットしながら先生にキスされ、敬虔な姉妹はその日限りでレッスンを断ってしまいます。ちなみにこの先生、公演シーンでは「セレナード」、鼻歌では「酒の歌」を歌うという『ドン・ジョヴァンニ』づくしですが、ほんとうはとても誠実な人で、原作によればキスもあくまでも役の上で気持ちが高ぶったとのこと。それに『ドン・ジョヴァンニ』でも「誘惑は未遂に終わる」ルールは守られているのですが。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『コシ・ファン・トゥッテ』
青年士官グリエルモとフェランドは自分の婚約者の貞節を信じ、女はみな移り気だと主張するドン・アルフォンソと賭けをする。二人は急に戦地に赴くことになったと芝居をうち、それぞれの婚約者で姉妹のフィオルディリージとドラベラは貞節を誓って彼らを見送る。男達はすぐに異国の貴族に変装して戻り姉妹を誘惑するが簡単にはなびかないので安心する。しかしアルフォンゾに協力する小間使いのデスピーナにもそそのかされるうち、姉妹はついに浮気してしまい、アルフォンソは「女はみなこうしたもの(コシ・ファン・トゥッテ)」と勝利を宣言する。男達は士官に早変わり、彼らの帰還が告げられて大混乱ののち、一同はめでたく和解する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『くたばれ』では『ドン・ジョヴァンニ』の興行失敗の後「今度はイタリアの他愛ない話だから大丈夫さ」と言って序曲を弾いて聴かせます。その言葉通り他愛ないお話で美しい重唱がゆったりたっぷり味わえるオペラ。『ハーモニー』(1996豪)は精神病院のセラピー活動で患者に『コシ』を上演させるというコメディ。元のオペラを知っていたほうが断然面白いので『コシ』を見てから是非。『マイ・レフトフット』(1989アイルランド)はフェランドが恋人の貞節を確信して歌うアリア「恋人の優しい息吹は」のレコードを左足でかけるシーンから始まります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『魔笛』
夜の女王から誘拐された娘パミーナの肖像画を見せられたタミーノは彼女を助け出すと誓う。鳥屋のパパゲーノも同行することになり二人には魔法の鈴と笛が与えられる。パミーナの捕えられているザラストロの神殿に入った二人は見張りに鈴で魔法をかけ彼女を救うが、出会った僧侶から、パミーナの父が亡くなる前に神殿の人々に託した「太陽の世界」を女王が取り戻そうとしているのだと聞かされる。女王はザラストロを殺すよう娘に命令するがザラストロは復讐でなく愛によって行動するよう説く。タミーノとパパゲーノは神殿の人となるための試練を魔笛の力を借りて乗り越え、それぞれの理想の女性パミーナ、パパゲーナと結ばれる。パミーナを力づくで取り戻そうとした女王は雷に打たれて奈落に落ち、太陽の世界の勝利を一同が祝って幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『くたばれ』ではザラストロの崇高なアリア「イシスとオシリスの神よ」が使われ、フリーメイソンを讃えた作品では?という扱いでしたが、『アマデウス』では妻コンスタンツェの母親が怒っているような「夜の女王のアリア」や、パパゲーノの「恋人か女房か」「パパパ」の楽しい場面、リハーサルでのバカ騒ぎも見せて、大衆向きオペラという点が強調されていました。『魔笛』といえば『愛の嵐』(1973伊/米)の二人が『魔笛』を上演中の劇場の離れた席でお互いを意識するシーンが有名。意外な所では『フェイス/オフ』(1997米)の凶悪犯ニコラス・ケイジが手術のビデオを見ているシーンに「憩いは死の中にしかない」と絶望を歌うパミーナのアリアが流れているのが謎です。
ここで少しだけ豆知識。『後宮』『魔笛』はドイツ語で書かれ、歌と台詞が完全に分けられたジングシュピール=歌芝居というスタイル。『フィガロ』『ドン・ジョヴァンニ』『コシ』はイタリア語で書かれ、台詞の部分も軽く歌うように作曲されていて、分類はオペラブッファ=喜歌劇(シリアスな要素もある『ドン・ジョヴァンニ』はドランマジョコーソ=諧謔劇とも呼ばれる)。この2つはモーツァルトが大きく発展させた大衆に人気のスタイルですが、補足するならモーツァルトは伝統的なオペラセリア=正歌劇にも『イドメネオ』『ティトの慈悲』などの傑作を残しています。台詞が歌われる点は同じですが、喜劇的な要素はなく神話や伝説的英雄を題材とする宮廷向きスタイルです(『イドメネオ』『ティト』はどちらも「慈悲」で終わるのでゴマスリ度も充分)。
さて『アマデウス』はアカデミー賞を8部門で獲得、主演男優賞にはトム・ハルスもノミネートされていましたがサリエリ役のエイブラハムが受賞しました。ハルスあってこその『アマデウス』なのに…彼のモーツァルトは天才への冒涜と受け取られたからとも言われますが、ではモーツァルト殺しのイメージが定着してしまったサリエリは冒涜じゃないのか?と考えるとやはりサリエリって可哀想。そのエイブラハムが殺し屋を演じた『ラストアクションヒーロー』(1993米)は映画と現実の世界がごっちゃになるパロディ&アクション?で、シュワルツェネッガーが初めて聴いたモーツァルト(『フィガロ』序曲)に感動して「あいつがモーツァルトを殺したのか?」と怒るのが笑えます。
『フィガロ』序曲は『大逆転』(1983米)で冒頭の朝の出勤シーンに使われ、タイヘンな騒動が起こりそうな感じを醸し出していました(エイクロイドが「伯爵がダンスなら」を口笛で吹くシーンも)。朝の出勤シーンといえばスコセッシ監督の『アフターアワーズ』(1985米)では、オペラではありませんがモーツァルトの「交響曲ニ長調」が異常な爽やかさで(?)響きます。
さて次回は、前回の斎藤さんにあえなく無視されてしまった『ニューヨークストーリー』第一話(スコセッシ監督)、『アマデウス』とアカデミー賞を競った『キリングフィールド』などに使われたプッチーニの『トゥーランドット』です。
◇『アマデウス』AMADEUS(1994米)
監督:ミロス・フォアマン
出演:トム・ハルス/F・マーレイ・エイブラハム
◇『くたばれアマデウス!』VERGESST MOZART(1994独)
監督:スラヴォ・ルーター
出演:アーミン・ミュラー=シュタール/マックス・ティドフ
◆『後宮からの誘拐』DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL(1782初演)3幕21曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ブレツナーの戯曲
台本:シュテファニー
◆『ドン・ジョヴァンニ』DON GIOVANNNI(1787初演)2幕26曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ドンファン伝説/ベルターティ「石の客」
台本:ダ=ポンテ
◆『コシ・ファン・トゥッテ』COSÌ FAN TUTTE(1790初演)2幕31曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:アリオスト「狂えるオルランド」ほか
台本:ダ=ポンテ
◆『魔笛』DIE ZAUBERFLÖTE(1791初演)2幕21曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ヴィーラント「ルル」ほか
台本:シカネーダー
 川北祥子(stravinsky ensemble)
川北祥子(stravinsky ensemble)
東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
ラリーフリント
『アマデウス』を初めて見たのは居酒屋のテレビでした。音大生が集まる居酒屋なので、何か曲が出てくるたびにみんなが叫んでイントロクイズのようでした。そんな見方もあるけど(?)クラシック音楽が好きじゃない人にも『アマデウス』は面白いし、同じフォアマン監督がポルノ雑誌の発行者の生涯(?)を描いた『ラリーフリント』(1996米)はポルノに興味がなくても面白い(というかポルノを期待する人にはハズレ)。『ラリー』にはドヴォルザークの『ルサルカ』のポロネーズや「スタバートマーテル」(ちょうど『アマデウス』の「レクイエム」のように)などが使われていて渋いです。ビデオの箱を持ってくレンタル屋さんではちょっと勇気がいるのが難点。
わかりやすく楽しく紹介するコラムです。
この映画もう一回見直してみよう、オペラっておもしろいんだね、って
少しでも思っていただけると嬉しいです。
映画を見たらオペラも見ようよ
第16回 アマデウスのいろいろありすぎてどれから見たらいいかわからないOPERAのすべてについて教えましょう
~で結局死因は?
『アマデウス』(1994米)はモーツァルトのミドルネームを広く知らしめ、サリエリにモーツァルト殺しのイメージを定着させました。偶然同年の『くたばれアマデウス!』(1984独)でもモーツァルト殺しの意外な真犯人が論じられました。死因はどちらもフィクションですがオペラに関するエピソードは事実に基づいているので、今回はこの二本に登場するモーツァルトのオペラベスト5『後宮からの誘拐』『フィガロの結婚』『ドン・ジョヴァンニ』『コシ・ファン・トゥッテ』『魔笛』を一挙にご紹介しましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『後宮からの誘拐』
貴族の娘コンスタンツェとその召し使いブロンデは航海中に海賊の捕虜となり、トルコの太守セリムに売られ彼の後宮に囲われているが、コンスタンツェは言い寄るセリムを断固として拒否し続けている。そこへコンスタンツェの恋人ベルモンテが召し使いペドリロから居場所を知らされて救出にかけつける。見張りのオスミンも簡単に眠らせ4人の脱出計画は成功するかに見えたがあと一息の所で捕まってしまい、さらにベルモンテの父がセリムと宿敵同士とわかり絶体絶命となるが、セリムは「悪には善によって報いよう」と4人を釈放し、全員がセリムの徳を讃えて幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
あのトム・ハルスのモーツァルトに「ハーレムが舞台で面白いんだよ」なんて言われると期待してしまいますがそれほどの話でもありません。「囲われている」と言いつつ、当時のお芝居では女性は「誘惑の危機」から「すんでのところで」逃れるというお約束になっていますからコンスタンツェも「まだ」無事で、ご丁寧にも「どんな拷問も死も(貞操を失うことに比べれば)怖くありません!」と立派なアリアを歌ってくれます。『アマデウス』に登場したのはこの2幕のアリアと3幕フィナーレ。フィナーレの意外な釈放は当時の「寛容な啓蒙君主」に対するゴマスリと言われ、つまりヨゼフ2世も大満足というわけです(音が多いとか文句言ってたのはテレ隠し?)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『フィガロの結婚』(ストーリーは第9回参照)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このコメディが「階級の間の対立を生む」(ヨゼフ2世)という実感は現在ではあまりありませんが、『くたばれ』での「伯爵がダンスならいつでもギターを弾いてやろう」というフィガロのアリアはとても皮肉っぽく聞こえます。『アマデウス』に出てきたのは冒頭の二重唱(リハーサル)、3幕フィナーレの結婚のバレエ、伯爵が許しを乞う4幕フィナーレ。フィナーレではアクビが大問題になっていましたが、3時間以上も聴いていれば面白くても疲れますよね?観に行く時には食事にも要注意。お腹がすいていては長時間耐えられないしお腹一杯だと眠ってしまうし…
『フィガロ』は特に有名なので映画への引用も数えきれませんが、その中で私のちょっと気になるのが4幕のバルバリーナの「なくしてしまったわ」というアリア。オペラの中では手紙を止めていたピンを落としてしまって探しているだけの小さな曲(貞操を失くしたという説もあるものの)ですが、『カオスシチリア物語』(1984伊)では母親の歌っていた曲として、『伴奏者』(1992仏)では歌手の夫のお気に入りの曲として、深い悲しみをもって流れます。ヨーロッパ映画でのこの使われ方には何か特別の意味があるのでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『ドン・ジョヴァンニ』
騎士長の屋敷に押し入ったドン・ジョヴァンニは、娘アンナを誘惑しようとして騎士長と決闘になり殺してしまう。アンナは恋人オッターヴィオとともに復讐を誓う。ドン・ジョヴァンニが次に声をかけたのは偶然にも彼に捨てられて追ってきたエルヴィラだったが、ドン・ジョヴァンニの従僕レポレロがうまく主人を逃がす。ドン・ジョヴァンニは村の花嫁ツェルリーナも誘惑するが失敗、ツェルリーナと花婿マゼットも彼を追う。皆から逃げたドン・ジョヴァンニの所へ騎士長の石像が現われ懺悔するように命令するが、ドン・ジョヴァンニが決然と断ると地獄の火が彼を包み込む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このオペラ最大の見せ場はやはり「ドン・ジョヴァンニの地獄落ち」でしょう。『虚栄のかがり火』(1990米)では逮捕目前まで追い詰められたトムハンクスが『ドン・ジョヴァンニ』を観に行き、地獄のかがり火の恐ろしいシーンに自分の姿を重ねていました。『アマデウス』でも煙が吹き出す演出(当時に可能?)。対照的にとても美しくて人気なのが二重唱「手をとりあって」。ジョニー・デップが自分をドンファンと思い込んでいる青年を演じる『ドンファン』(1995米)ではあくまでもロマンティックに使われていましたが、実際には誘惑するドン・ジョヴァンニと結婚式当日というのに誘いに乗ってしまうツェルリーナの二重唱なのでもう少し複雑な意味合い。『郵便配達は二度ベルを鳴らす』(1981米)のジェシカ・ラングは夫が寝室でこの曲のレコードをかけているのでニコルソンの誘いに乗れません。『バベットの晩餐会』(1987デンマーク)では歌のレッスンでこの曲をデュエットしながら先生にキスされ、敬虔な姉妹はその日限りでレッスンを断ってしまいます。ちなみにこの先生、公演シーンでは「セレナード」、鼻歌では「酒の歌」を歌うという『ドン・ジョヴァンニ』づくしですが、ほんとうはとても誠実な人で、原作によればキスもあくまでも役の上で気持ちが高ぶったとのこと。それに『ドン・ジョヴァンニ』でも「誘惑は未遂に終わる」ルールは守られているのですが。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『コシ・ファン・トゥッテ』
青年士官グリエルモとフェランドは自分の婚約者の貞節を信じ、女はみな移り気だと主張するドン・アルフォンソと賭けをする。二人は急に戦地に赴くことになったと芝居をうち、それぞれの婚約者で姉妹のフィオルディリージとドラベラは貞節を誓って彼らを見送る。男達はすぐに異国の貴族に変装して戻り姉妹を誘惑するが簡単にはなびかないので安心する。しかしアルフォンゾに協力する小間使いのデスピーナにもそそのかされるうち、姉妹はついに浮気してしまい、アルフォンソは「女はみなこうしたもの(コシ・ファン・トゥッテ)」と勝利を宣言する。男達は士官に早変わり、彼らの帰還が告げられて大混乱ののち、一同はめでたく和解する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『くたばれ』では『ドン・ジョヴァンニ』の興行失敗の後「今度はイタリアの他愛ない話だから大丈夫さ」と言って序曲を弾いて聴かせます。その言葉通り他愛ないお話で美しい重唱がゆったりたっぷり味わえるオペラ。『ハーモニー』(1996豪)は精神病院のセラピー活動で患者に『コシ』を上演させるというコメディ。元のオペラを知っていたほうが断然面白いので『コシ』を見てから是非。『マイ・レフトフット』(1989アイルランド)はフェランドが恋人の貞節を確信して歌うアリア「恋人の優しい息吹は」のレコードを左足でかけるシーンから始まります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆『魔笛』
夜の女王から誘拐された娘パミーナの肖像画を見せられたタミーノは彼女を助け出すと誓う。鳥屋のパパゲーノも同行することになり二人には魔法の鈴と笛が与えられる。パミーナの捕えられているザラストロの神殿に入った二人は見張りに鈴で魔法をかけ彼女を救うが、出会った僧侶から、パミーナの父が亡くなる前に神殿の人々に託した「太陽の世界」を女王が取り戻そうとしているのだと聞かされる。女王はザラストロを殺すよう娘に命令するがザラストロは復讐でなく愛によって行動するよう説く。タミーノとパパゲーノは神殿の人となるための試練を魔笛の力を借りて乗り越え、それぞれの理想の女性パミーナ、パパゲーナと結ばれる。パミーナを力づくで取り戻そうとした女王は雷に打たれて奈落に落ち、太陽の世界の勝利を一同が祝って幕となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『くたばれ』ではザラストロの崇高なアリア「イシスとオシリスの神よ」が使われ、フリーメイソンを讃えた作品では?という扱いでしたが、『アマデウス』では妻コンスタンツェの母親が怒っているような「夜の女王のアリア」や、パパゲーノの「恋人か女房か」「パパパ」の楽しい場面、リハーサルでのバカ騒ぎも見せて、大衆向きオペラという点が強調されていました。『魔笛』といえば『愛の嵐』(1973伊/米)の二人が『魔笛』を上演中の劇場の離れた席でお互いを意識するシーンが有名。意外な所では『フェイス/オフ』(1997米)の凶悪犯ニコラス・ケイジが手術のビデオを見ているシーンに「憩いは死の中にしかない」と絶望を歌うパミーナのアリアが流れているのが謎です。
ここで少しだけ豆知識。『後宮』『魔笛』はドイツ語で書かれ、歌と台詞が完全に分けられたジングシュピール=歌芝居というスタイル。『フィガロ』『ドン・ジョヴァンニ』『コシ』はイタリア語で書かれ、台詞の部分も軽く歌うように作曲されていて、分類はオペラブッファ=喜歌劇(シリアスな要素もある『ドン・ジョヴァンニ』はドランマジョコーソ=諧謔劇とも呼ばれる)。この2つはモーツァルトが大きく発展させた大衆に人気のスタイルですが、補足するならモーツァルトは伝統的なオペラセリア=正歌劇にも『イドメネオ』『ティトの慈悲』などの傑作を残しています。台詞が歌われる点は同じですが、喜劇的な要素はなく神話や伝説的英雄を題材とする宮廷向きスタイルです(『イドメネオ』『ティト』はどちらも「慈悲」で終わるのでゴマスリ度も充分)。
さて『アマデウス』はアカデミー賞を8部門で獲得、主演男優賞にはトム・ハルスもノミネートされていましたがサリエリ役のエイブラハムが受賞しました。ハルスあってこその『アマデウス』なのに…彼のモーツァルトは天才への冒涜と受け取られたからとも言われますが、ではモーツァルト殺しのイメージが定着してしまったサリエリは冒涜じゃないのか?と考えるとやはりサリエリって可哀想。そのエイブラハムが殺し屋を演じた『ラストアクションヒーロー』(1993米)は映画と現実の世界がごっちゃになるパロディ&アクション?で、シュワルツェネッガーが初めて聴いたモーツァルト(『フィガロ』序曲)に感動して「あいつがモーツァルトを殺したのか?」と怒るのが笑えます。
『フィガロ』序曲は『大逆転』(1983米)で冒頭の朝の出勤シーンに使われ、タイヘンな騒動が起こりそうな感じを醸し出していました(エイクロイドが「伯爵がダンスなら」を口笛で吹くシーンも)。朝の出勤シーンといえばスコセッシ監督の『アフターアワーズ』(1985米)では、オペラではありませんがモーツァルトの「交響曲ニ長調」が異常な爽やかさで(?)響きます。
さて次回は、前回の斎藤さんにあえなく無視されてしまった『ニューヨークストーリー』第一話(スコセッシ監督)、『アマデウス』とアカデミー賞を競った『キリングフィールド』などに使われたプッチーニの『トゥーランドット』です。
◇『アマデウス』AMADEUS(1994米)
監督:ミロス・フォアマン
出演:トム・ハルス/F・マーレイ・エイブラハム
◇『くたばれアマデウス!』VERGESST MOZART(1994独)
監督:スラヴォ・ルーター
出演:アーミン・ミュラー=シュタール/マックス・ティドフ
◆『後宮からの誘拐』DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL(1782初演)3幕21曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ブレツナーの戯曲
台本:シュテファニー
◆『ドン・ジョヴァンニ』DON GIOVANNNI(1787初演)2幕26曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ドンファン伝説/ベルターティ「石の客」
台本:ダ=ポンテ
◆『コシ・ファン・トゥッテ』COSÌ FAN TUTTE(1790初演)2幕31曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:アリオスト「狂えるオルランド」ほか
台本:ダ=ポンテ
◆『魔笛』DIE ZAUBERFLÖTE(1791初演)2幕21曲
作曲:モーツァルト W.A.Mozart(1756-91)
原作:ヴィーラント「ルル」ほか
台本:シカネーダー

東京芸術大学大学院修了、「トムとジェリー」とB級映画とパンダを愛するピアノ奏者。
「トムとジェリー」からはクラシック音楽の神髄を、
B級映画からはお金がなくても面白いコトに挑戦する心意気を学ぶ。
パンダからは…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*オマケ話(gingapanda掲載の連動コラム)
ラリーフリント
『アマデウス』を初めて見たのは居酒屋のテレビでした。音大生が集まる居酒屋なので、何か曲が出てくるたびにみんなが叫んでイントロクイズのようでした。そんな見方もあるけど(?)クラシック音楽が好きじゃない人にも『アマデウス』は面白いし、同じフォアマン監督がポルノ雑誌の発行者の生涯(?)を描いた『ラリーフリント』(1996米)はポルノに興味がなくても面白い(というかポルノを期待する人にはハズレ)。『ラリー』にはドヴォルザークの『ルサルカ』のポロネーズや「スタバートマーテル」(ちょうど『アマデウス』の「レクイエム」のように)などが使われていて渋いです。ビデオの箱を持ってくレンタル屋さんではちょっと勇気がいるのが難点。


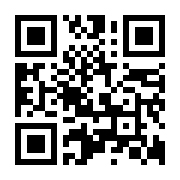
最近のコメント