素敵な作品たち ― 2025-10-18
ラヴェルの「クレマン・マロのエピグラム」は、前奏からして印象的な二曲であり、一曲目は凍てついた冬の空気を感じ、二曲目はスピネットでの演奏が目に浮かぶ。二曲とも短いながら非常に洗練されていて、歌詞の部分の流れるようなメロディやコンパクトな構成はクレマン・マロの詩に余計な肉付けをせず、必要最低限で完全に音楽にしたように感じる。しかし、前奏が詩の内容を予感させ後奏が詩の余韻を残すことでたっぷりと詩に浸ることができる。
エネスクの「クレマン・マロの七つのシャンソン」は初めて見た時、一曲ごとの雰囲気の違いとその配置(曲順)や長さにおいて、7曲のバランスの良さがとても魅力的に思えた。メロディラインも複雑な転調や拍が耳に心地よく、これは歌ってみたい、とすぐに思った。またピアノパートもそれだけで一曲になりそうに繊細で美しい。恋に苦悩し、わずかに垣間見える幸福感、報われない運命という暗めの雰囲気の詩に、突然ぶどうの蔓を切る鎌を讃える詩を差し込んでいるところも面白い。
上の二曲はルネサンスの詩であるため、発音がよく分からないところがある。そこでAIにお尋ねして大体の傾向を把握し、自分なりの一応の基準を設けることにした。今回は面白がっていろいろAIにお尋ねしたが、尋ねてもいない音楽的・演出的ヒントまでアドバイスされて驚いた…上記のエネスクのバラの歌では「舞台上に白と赤のバラを配置」、鎌を讃える歌では「舞台演出:ぶどうの蔓、鎌、ワインの小道具を使って視覚的に物語を補強」、終曲では「声の表現:抑制された感情、語るようなトーン、演出:舞台の照明を徐々に暗くし、最後の一行で完全な静寂へ」など…面白く読んだが、残念ながら採用するには至っていない。
サティの3つのヴォカリーズは、「羊」「鳥たち」「馬」に関係のある題名と音のつながりがあまりピンとこなかったが、この曲が作曲されたのはサティが「家具の音楽」という「聴かれることを目的としていない音楽」を提唱した時期に当たるとのこと。環境音楽の走りである。その昔私は、誰が歌っているか問題にしないような、まわりに溶け込むような歌を歌いたい、と人に話したことがあったが、まさにこれのことではないか、といまさらながらに気がついた。それはさておき、ヴォカリーズはメロディに酔いしれて声を聴かせるイメージ(偏見)があるが、この曲はそういう感じでもなく、どう歌おうか悩んでしまった。しかし「家具の音楽」の産物だとしたら、ロールプレイングゲームの村や平原の曲のように永遠に繰り返されても耳障りでない、そんなふうに歌おうかと思う。
コスマの「トリスタンの動物園」、今回ようやく全曲まとめて取り組むが、並べてみるとこれも面白い曲集であった。言葉遊びのようであっても物語がある。芝居っ気が求められるところが(私にとっては)玉に瑕だが、フランス語の抑揚やメロディとピアノがきっと補ってくれる。
ところで今回は、アンヌとは誰か、トリスタンとは誰か、ランブイエ、マリエンバードも本当のところは何を指すのか、いろいろと謎は多いままだ。AIも確かなことは言えない、と前置きがある。でも素敵な作品なのは確かなことだ。
--------------------------------------------------
*今月の演奏メニュー
2025年10月26日(日) 10時30分開演 (10時10分開場 11時30分終演予定)
於:本郷・金魚坂 (新店舗) / コーヒーまたは中国茶つき 1,800円
cafconc第168回
アンヌと動物たち〜my favorite songs
ラヴェル「クレマン・マロの2つのエピグラム」
雪を投げるアンヌ
スピネットを弾くアンヌ
エネスク「クレマン・マロの7つのシャンソン」
Estrene a Anne
Languir me fais...
Aux damoyselles paresseuses d'escrire a leurs amys
Estrene de la rose
Present de couleur blanche
Changeons propos, c'est trop chanté d'amours
Du confict en douleur
サティ「3つの無言歌」
マリエンバート
鳥たち
ランブイエ
コスマ「トリスタンの動物園」(全5曲)
穴のあいた靴をはいた蛙
何にも似ていない猫
コロラドの鳥
心配のない魚
口髭のある蜘蛛
ほか
渡辺有里香(ソプラノ)
川北祥子(ピアノ)
ゲスト:江草智子(ファゴット)
--------------------------------------------------
エネスクの「クレマン・マロの七つのシャンソン」は初めて見た時、一曲ごとの雰囲気の違いとその配置(曲順)や長さにおいて、7曲のバランスの良さがとても魅力的に思えた。メロディラインも複雑な転調や拍が耳に心地よく、これは歌ってみたい、とすぐに思った。またピアノパートもそれだけで一曲になりそうに繊細で美しい。恋に苦悩し、わずかに垣間見える幸福感、報われない運命という暗めの雰囲気の詩に、突然ぶどうの蔓を切る鎌を讃える詩を差し込んでいるところも面白い。
上の二曲はルネサンスの詩であるため、発音がよく分からないところがある。そこでAIにお尋ねして大体の傾向を把握し、自分なりの一応の基準を設けることにした。今回は面白がっていろいろAIにお尋ねしたが、尋ねてもいない音楽的・演出的ヒントまでアドバイスされて驚いた…上記のエネスクのバラの歌では「舞台上に白と赤のバラを配置」、鎌を讃える歌では「舞台演出:ぶどうの蔓、鎌、ワインの小道具を使って視覚的に物語を補強」、終曲では「声の表現:抑制された感情、語るようなトーン、演出:舞台の照明を徐々に暗くし、最後の一行で完全な静寂へ」など…面白く読んだが、残念ながら採用するには至っていない。
サティの3つのヴォカリーズは、「羊」「鳥たち」「馬」に関係のある題名と音のつながりがあまりピンとこなかったが、この曲が作曲されたのはサティが「家具の音楽」という「聴かれることを目的としていない音楽」を提唱した時期に当たるとのこと。環境音楽の走りである。その昔私は、誰が歌っているか問題にしないような、まわりに溶け込むような歌を歌いたい、と人に話したことがあったが、まさにこれのことではないか、といまさらながらに気がついた。それはさておき、ヴォカリーズはメロディに酔いしれて声を聴かせるイメージ(偏見)があるが、この曲はそういう感じでもなく、どう歌おうか悩んでしまった。しかし「家具の音楽」の産物だとしたら、ロールプレイングゲームの村や平原の曲のように永遠に繰り返されても耳障りでない、そんなふうに歌おうかと思う。
コスマの「トリスタンの動物園」、今回ようやく全曲まとめて取り組むが、並べてみるとこれも面白い曲集であった。言葉遊びのようであっても物語がある。芝居っ気が求められるところが(私にとっては)玉に瑕だが、フランス語の抑揚やメロディとピアノがきっと補ってくれる。
ところで今回は、アンヌとは誰か、トリスタンとは誰か、ランブイエ、マリエンバードも本当のところは何を指すのか、いろいろと謎は多いままだ。AIも確かなことは言えない、と前置きがある。でも素敵な作品なのは確かなことだ。
--------------------------------------------------
*今月の演奏メニュー
2025年10月26日(日) 10時30分開演 (10時10分開場 11時30分終演予定)
於:本郷・金魚坂 (新店舗) / コーヒーまたは中国茶つき 1,800円
cafconc第168回
アンヌと動物たち〜my favorite songs
ラヴェル「クレマン・マロの2つのエピグラム」
雪を投げるアンヌ
スピネットを弾くアンヌ
エネスク「クレマン・マロの7つのシャンソン」
Estrene a Anne
Languir me fais...
Aux damoyselles paresseuses d'escrire a leurs amys
Estrene de la rose
Present de couleur blanche
Changeons propos, c'est trop chanté d'amours
Du confict en douleur
サティ「3つの無言歌」
マリエンバート
鳥たち
ランブイエ
コスマ「トリスタンの動物園」(全5曲)
穴のあいた靴をはいた蛙
何にも似ていない猫
コロラドの鳥
心配のない魚
口髭のある蜘蛛
ほか
渡辺有里香(ソプラノ)
川北祥子(ピアノ)
ゲスト:江草智子(ファゴット)
--------------------------------------------------


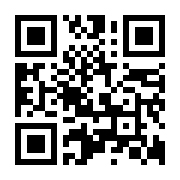
最近のコメント